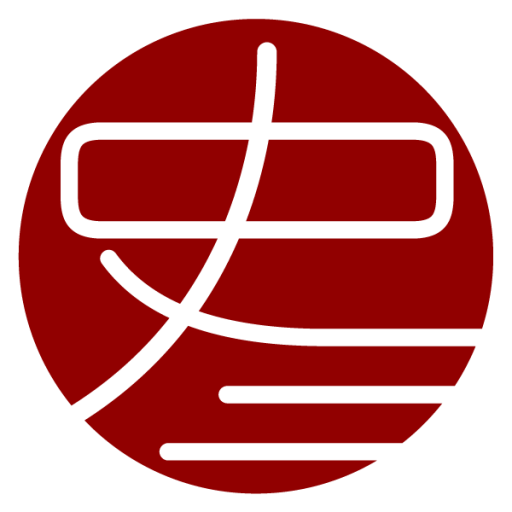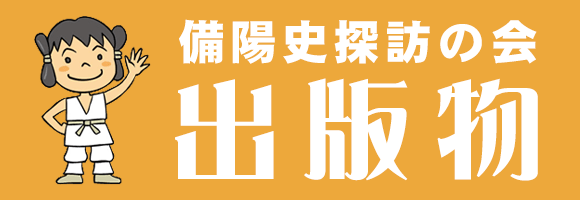「備陽史探訪:19号」より
山口 哲晶
古墳による祭祀が、初期における首長の霊を祀る共同体の集団祭祀としての性格から、内制的な支配者の権力を誇示する単なる厚葬に変化したことは、その副葬品の変化により知る事ができる。それは、より権力的な支配の確立をめざし、新たな政治的、階級的な権威をもって人民にのぞもうとする首長層の動向を反映しているのである。その為、古墳の規模も次第に巨大化の方向に向い、その規模、構造及び副葬品に於てそれらがそのまま権力及び財力の強弱としてあらわれてくる様になる。
そういう状況に於て、次第に古墳を築造できる階級層が下層まで拡がって行く。つまり今まで首長クラスしか築造できなかった古墳が、もっと小規模な家長クラスにまで築造できる様な状況になった。その背景には、新しい技術、用具の普及による農業生産力の増大によるものが大きいといえよう。
この為、古墳というものが権力、財力の象徴としての意味を次第に失い、古墳の乱築を招いて行った。そこで、時の朝廷は大化二年(六四六年)に薄葬令を発布し、身分により古墳の規模、労役日数、労役人数等の制限を加え、古墳の乱築に歯止めをかけようと試みている。しかしながら、その後も多くの豪族達は、自己の権力、財力の誇示の為に従来通り古墳を築造し続けているという事は、この法令による効果は少なかったと言える。
ところが、五三八年(五五二年という説もあり)に伝来したとされる仏教に於て、その思想が次第に古墳築造を終末へと向かわしめた様である。すなわち仏教の思想に於ては、人が死ぬと肉体はけがれとして扱われ霊を重要視するのである。その為、肉体を葬る古墳という建築物が前時代的な存在としてみられる様になり、逆に霊をまつる寺院の建立へと豪族達の権力、財力の誇示の方法がとられはじめてゆくのである。外に向っては古墳をつくり、内に向っては寺院を建立するという期間をへて、やがて豪族達の財力は自らの氏寺建立へと向けられ、古墳は次第に終末を迎えるのである。
https://bingo-history.net/archives/30406https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/04/3dd12eea04000b710386ed516ea3bba8.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/04/3dd12eea04000b710386ed516ea3bba8-150x100.jpg管理人古代史「備陽史探訪:19号」より
山口 哲晶
古墳による祭祀が、初期における首長の霊を祀る共同体の集団祭祀としての性格から、内制的な支配者の権力を誇示する単なる厚葬に変化したことは、その副葬品の変化により知る事ができる。それは、より権力的な支配の確立をめざし、新たな政治的、階級的な権威をもって人民にのぞもうとする首長層の動向を反映しているのである。その為、古墳の規模も次第に巨大化の方向に向い、その規模、構造及び副葬品に於てそれらがそのまま権力及び財力の強弱としてあらわれてくる様になる。
そういう状況に於て、次第に古墳を築造できる階級層が下層まで拡がって行く。つまり今まで首長クラスしか築造できなかった古墳が、もっと小規模な家長クラスにまで築造できる様な状況になった。その背景には、新しい技術、用具の普及による農業生産力の増大によるものが大きいといえよう。
この為、古墳というものが権力、財力の象徴としての意味を次第に失い、古墳の乱築を招いて行った。そこで、時の朝廷は大化二年(六四六年)に薄葬令を発布し、身分により古墳の規模、労役日数、労役人数等の制限を加え、古墳の乱築に歯止めをかけようと試みている。しかしながら、その後も多くの豪族達は、自己の権力、財力の誇示の為に従来通り古墳を築造し続けているという事は、この法令による効果は少なかったと言える。
ところが、五三八年(五五二年という説もあり)に伝来したとされる仏教に於て、その思想が次第に古墳築造を終末へと向かわしめた様である。すなわち仏教の思想に於ては、人が死ぬと肉体はけがれとして扱われ霊を重要視するのである。その為、肉体を葬る古墳という建築物が前時代的な存在としてみられる様になり、逆に霊をまつる寺院の建立へと豪族達の権力、財力の誇示の方法がとられはじめてゆくのである。外に向っては古墳をつくり、内に向っては寺院を建立するという期間をへて、やがて豪族達の財力は自らの氏寺建立へと向けられ、古墳は次第に終末を迎えるのである。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会
備陽史探訪の会古代史部会では「大人の博物館教室」と題して定期的に勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
大人の博物館教室