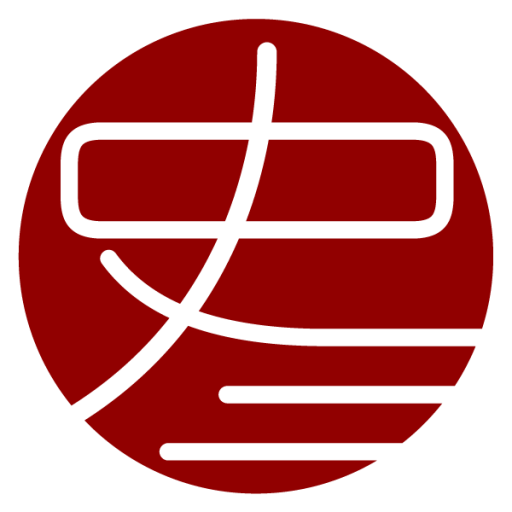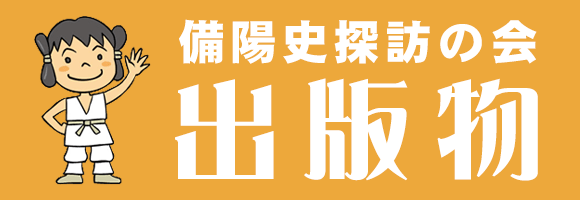「福山の遺跡一〇〇選」より
篠原 芳秀
 廃慶徳寺跡 塔の心礎
廃慶徳寺跡 塔の心礎福山市新市町大字戸手に所在する。寺跡の範囲は、JR福塩線の上戸手駅から約四〇〇m東方にある福塩線と県道下御領新市線が立体交差する地点体交差する地点(以下、「立体交差」という。)付近から北東側に広がる区域が想定されている(1)。
大正三(一九一四)年に福山‐府中間が開通した両備軽便鉄道(現在の福塩線)の工事によって塔の心礎や多くの礎石・瓦等が掘り出されたようである。豊元國氏は
塔の土壇が少しばかり遺っており、心礎が二個発見されている。(2)
民神社のすぐ東隣りにも寺址があって礎石が掘りおこされ瓦が散布している。瓦は塔址のものと同じであるから、塔と金堂ぐらいをもつ地方の小寺院であったと考えてよい。(3)
また村上正名氏は
中心礎石の出土で塔址と考えられる土壇址の一部が現存して小祠が祭られて、二本の老松がそびえている。(中略)なお、北方の艮神社の東側の民家の裏山に瓦窯址が三カ所に存在したが、一つは大正年間に破壊され、他の一つは現在竹薮中に遺存する。(4)
と記されている。
塔の基壇と思われるところは確認できないが、土地の古老によれば、立体交差の南側にある小さな祠の神箭神社あたりに「以前、老松が二本あった。祠はもっと線路寄りにあった。」と話されており、このあたりに塔跡が位置していた可能性は高い。そして、寺域は北東方向に広がっていたものであろう。ほかの建物跡や瓦窯跡についても確認することはできない。
塔の心礎は、長さ約一一〇Cm、幅約七五cm、厚さ約四〇cmの石の上面に直径約六〇cm、高さ一・六mの円形造り出しを設け、その中心に直径二〇cm、深さ四・二cmの柄穴を穿つたもので、艮神社の境内にある金刀比羅宮碑の台石として転用されている。さらに、艮神社から約一血東方の信岡家にある円形造り出しをもつ礎石も、当寺跡から運ばれたものであろう。
採集されている瓦に素弁蓮華文軒丸瓦があり、創建は七世紀後半でも早い年代と思われる。そして、平安時代の瓦もあることから、そのころまで存続したのであろう。
この寺跡については、福山市しんいち歴史民俗博物館に展示されている。
車では、国道四八六号線の「戸手高校入口」交差点から北に約五〇Om行くと艮神社がある。周辺に駐車場はないので、境内に駐車させていただき、参拝してから寺跡を訪ねよう。
(1)『新市町史』資料編I 二〇〇二年
(2)豊元國「解説」『社会科標本室給葉書 第四輯 備後の古瓦特輯』広島県立府中高等学校生徒会 一九五九年
(3)豊元國「解説」『学校博物館絵はがき 第一〇輯』広島県立府中高等学校生徒会 一九六五年
(4)村上正名「廃慶徳寺址」『福山市史』上巻 一九六三年
【廃慶徳寺跡】
https://bingo-history.net/archives/15902https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/03/308d1655ec812f67a9d6690af03f899d.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/03/308d1655ec812f67a9d6690af03f899d-150x100.jpg管理人古代史「福山の遺跡一〇〇選」より
篠原 芳秀 福山市新市町大字戸手に所在する。寺跡の範囲は、JR福塩線の上戸手駅から約四〇〇m東方にある福塩線と県道下御領新市線が立体交差する地点体交差する地点(以下、「立体交差」という。)付近から北東側に広がる区域が想定されている(1)。 大正三(一九一四)年に福山‐府中間が開通した両備軽便鉄道(現在の福塩線)の工事によって塔の心礎や多くの礎石・瓦等が掘り出されたようである。豊元國氏は 塔の土壇が少しばかり遺っており、心礎が二個発見されている。(2) 民神社のすぐ東隣りにも寺址があって礎石が掘りおこされ瓦が散布している。瓦は塔址のものと同じであるから、塔と金堂ぐらいをもつ地方の小寺院であったと考えてよい。(3) また村上正名氏は 中心礎石の出土で塔址と考えられる土壇址の一部が現存して小祠が祭られて、二本の老松がそびえている。(中略)なお、北方の艮神社の東側の民家の裏山に瓦窯址が三カ所に存在したが、一つは大正年間に破壊され、他の一つは現在竹薮中に遺存する。(4) と記されている。 塔の基壇と思われるところは確認できないが、土地の古老によれば、立体交差の南側にある小さな祠の神箭神社あたりに「以前、老松が二本あった。祠はもっと線路寄りにあった。」と話されており、このあたりに塔跡が位置していた可能性は高い。そして、寺域は北東方向に広がっていたものであろう。ほかの建物跡や瓦窯跡についても確認することはできない。 塔の心礎は、長さ約一一〇Cm、幅約七五cm、厚さ約四〇cmの石の上面に直径約六〇cm、高さ一・六mの円形造り出しを設け、その中心に直径二〇cm、深さ四・二cmの柄穴を穿つたもので、艮神社の境内にある金刀比羅宮碑の台石として転用されている。さらに、艮神社から約一血東方の信岡家にある円形造り出しをもつ礎石も、当寺跡から運ばれたものであろう。 採集されている瓦に素弁蓮華文軒丸瓦があり、創建は七世紀後半でも早い年代と思われる。そして、平安時代の瓦もあることから、そのころまで存続したのであろう。 この寺跡については、福山市しんいち歴史民俗博物館に展示されている。 車では、国道四八六号線の「戸手高校入口」交差点から北に約五〇Om行くと艮神社がある。周辺に駐車場はないので、境内に駐車させていただき、参拝してから寺跡を訪ねよう。 (1)『新市町史』資料編I 二〇〇二年
(2)豊元國「解説」『社会科標本室給葉書 第四輯 備後の古瓦特輯』広島県立府中高等学校生徒会 一九五九年
(3)豊元國「解説」『学校博物館絵はがき 第一〇輯』広島県立府中高等学校生徒会 一九六五年
(4)村上正名「廃慶徳寺址」『福山市史』上巻 一九六三年 【廃慶徳寺跡】 管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会
備陽史探訪の会古代史部会では「大人の博物館教室」と題して定期的に勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
大人の博物館教室