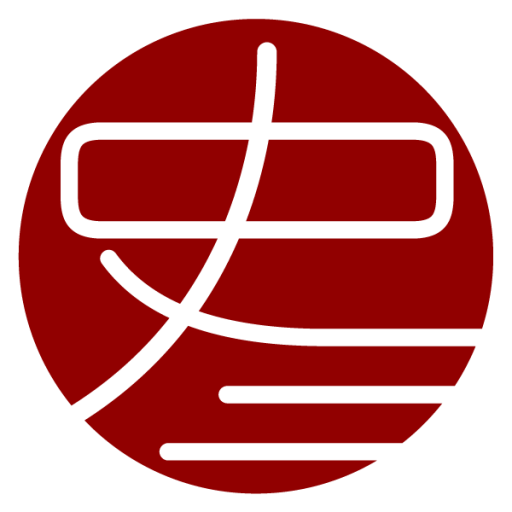【Web限定特別寄稿】考古学的観点から見た会報『備陽史探訪』について
せっかく会報[備陽史探訪]の全号検索ができるようになりましたので、備陽史探訪の楽しみ方として会報の変遷について考古学的アプローチから迫ったシン・ターナー氏の研究を掲載したいと思います。
考古学的観点から見た会報『備陽史探訪』について
シン・ターナー(2012年7月)
現在までの「備陽史探訪」を編年する場合、その紙面には2度の大きな変革があり、これを境として3期(前期、中期、後期)に分類することができます。そして、この2度の変革を紐解いていく段階で1度目と2度目とでは発生要因が大きく異なる可能性が極めて高いことがわかりました。そこで、以下において備陽史探訪の変遷を通してこの変革の本質に迫りたいと思います。

まず、前期備陽史探訪(1号~29号)の特徴を見ると「手書き」であることに気が付きます。紙面は自由かつ荒削りな構成となっており、文字の可読性も執筆者の個性により大きく異なっています。また、発行間隔も毎月から長いときは約1年もの間隔があるなど、発行の安定性も比較的低い様子が読み取れます。
内容については、2号においては丸々「スキーのすべり方」であったり、「突撃ルポ」と呼ばれる娯楽性に富んだ企画が組まれるなど、制約が殆ど見られず闊達な状況であったことが強く伺えます。この時期の備陽史探訪を例えるなら「執筆者の時代」といえるでしょう。なお、極初期(1~3号)においてはタイプ印刷が持ちられていますが、当時のタイプは100万円超の機材であったはずで、継続した使用までには至らなかったようです。
前期備陽史探訪も20号あたりになると記事数が安定しページ数も概ね12~24ページで推移するようになりますが、30号で活字(写植印刷)という新たな技術が導入され、備陽史探訪の中期(30号~102号)時代が始まります。

活字化により、紙面表層部からは前期特有の奔放な雰囲気は姿を消しますが、文字の可読性は劇的に高まります。また、文字サイズについても手書きの約半分、面積でいえば1/4に圧縮されたため、段組等を考慮してもページ当たりの情報密度(文字数)が3倍超へと増加します。このため、ページ数は中期に入り1桁(6~8ページ)へと減少します。ただし、この頃には会員数が右肩上がりで増えていたこともあり、記事数は断続的に増加していき、43号でページ数は再び2桁に転じます。
その後のページ数は概ね10~16ページ程度で安定しますが、60号では過去最高の22ページ、69号ではそれを上回る24ページ、更に100号では26ページを記録するなど、要所には前期には見られない巨大な会報が出現します。このため、中期は「巨大会報の時代」だといえます。また、内容については前期とは別の意味で多様性に富んだものになり、前期の「執筆者の時代」に対して中期は「読者の時代」とも言えるでしょう。
しかし、読者の時代は編集者にとっては苦難の時代でもあったようです。というのは、手書き時代と同等のページ数に戻るということは、逆に言えば文書量が手書き時代の3倍超になっていることでもあり、当時のOA機器の普及水準から考えると原稿は手書きが大半だったはずですので、その作業量は膨大なものであったに違いないからです。
実際、紙面においても度々「ワープロの打てる方」の支援が求められており、70号からは「持ちまわり」で編集を行うようになるなど、その様子が垣間見えます。我々がこの時代の会報を目にするとき、その裏には編集者の多大な苦労があることを忘れてはなりません。
さて、このようにして、ある意味黄金期を迎えた備陽史探訪に第2の変革の波が押し寄せます。渡来系用紙規格(A4サイズ)の導入です。この規格は103号から始まり現在まで続くもので、在地系規格(B5サイズ)の中期以前に比べ紙の面積が約1.3倍に拡大することになります。しかし、前期から中期への1度目の変革時と本質的に大きく異なっているのは、この面積の拡大が文字数の増加に使われるのではなく、文字サイズの拡大(9→10pt)という逆の方向に使われたことです。
では、2度目の変革はどうして1度目と方向性が異なったのでしょうか?その背景を探ると、1度目が編集側の積極的な意志が示されるのに対して、2度目は編集側の強い意志が読み取れないことが見えてきます。
というのは、読者にとっては2度目の変革(渡来系規格導入)は紙面の視認性を飛躍的に向上させるもので、外面的なインパクトとしては1度目(活字化)に匹敵するものですが、他方で編集側の観点からは2度目の変革は影響が極めて小規模なものなのです。やや逆説的になるのですが、1度目の変革には編集側に主体的な活動が求められますが、2度目は能動的な動きを必要とせず、それ以外の外的要因の働いた蓋然性が高いと推察できるのです。そして、当時の出版業界の情勢を鑑みれば渡来系文化(A版)普及の一端として2度目の変革が備陽史探訪に波及した可能性が浮かび上がってきます。このことは103号の編集後記に「ええ~い、国際社会をなんと心得おる、大きくしちゃえ」と記されるなど、文献からも裏付けられます。
言い換えるなら、1度目の変革が中からの変革であるのに対し、2度目の変革は外からの変革といえるでしょう。
こうした2度の変革を経て後期に入ると、備陽史探訪は円熟期ともいえる時期を迎えます。内容、ページ数、発行間隔も現在まで長期に安定しており、私はこの平和期を「パクス・ビヨウシーナ(備陽史探訪の平和)」と呼称することを提唱したいと思います。
以上、これまでの備陽史探訪を大きな流れで考察しましたが、前期過程の中で突発的に発生し消滅した備探通信など、まだまだ未解明な部分も多く今後の研究の進展が期待されます。
※この記事はネタです。
https://bingo-history.net/archives/4335https://bingo-history.net/wp-content/uploads/1984/07/6649c3acc27e3e4433653bfdad7d9a62.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/1984/07/6649c3acc27e3e4433653bfdad7d9a62-150x100.jpg事務局だより事務局だよりせっかく会報[備陽史探訪]の全号検索ができるようになりましたので、備陽史探訪の楽しみ方として会報の変遷について考古学的アプローチから迫ったシン・ターナー氏の研究を掲載したいと思います。 考古学的観点から見た会報『備陽史探訪』について シン・ターナー(2012年7月) 現在までの「備陽史探訪」を編年する場合、その紙面には2度の大きな変革があり、これを境として3期(前期、中期、後期)に分類することができます。そして、この2度の変革を紐解いていく段階で1度目と2度目とでは発生要因が大きく異なる可能性が極めて高いことがわかりました。そこで、以下において備陽史探訪の変遷を通してこの変革の本質に迫りたいと思います。 まず、前期備陽史探訪(1号~29号)の特徴を見ると「手書き」であることに気が付きます。紙面は自由かつ荒削りな構成となっており、文字の可読性も執筆者の個性により大きく異なっています。また、発行間隔も毎月から長いときは約1年もの間隔があるなど、発行の安定性も比較的低い様子が読み取れます。 内容については、2号においては丸々「スキーのすべり方」であったり、「突撃ルポ」と呼ばれる娯楽性に富んだ企画が組まれるなど、制約が殆ど見られず闊達な状況であったことが強く伺えます。この時期の備陽史探訪を例えるなら「執筆者の時代」といえるでしょう。なお、極初期(1~3号)においてはタイプ印刷が持ちられていますが、当時のタイプは100万円超の機材であったはずで、継続した使用までには至らなかったようです。 前期備陽史探訪も20号あたりになると記事数が安定しページ数も概ね12~24ページで推移するようになりますが、30号で活字(写植印刷)という新たな技術が導入され、備陽史探訪の中期(30号~102号)時代が始まります。 活字化により、紙面表層部からは前期特有の奔放な雰囲気は姿を消しますが、文字の可読性は劇的に高まります。また、文字サイズについても手書きの約半分、面積でいえば1/4に圧縮されたため、段組等を考慮してもページ当たりの情報密度(文字数)が3倍超へと増加します。このため、ページ数は中期に入り1桁(6~8ページ)へと減少します。ただし、この頃には会員数が右肩上がりで増えていたこともあり、記事数は断続的に増加していき、43号でページ数は再び2桁に転じます。 その後のページ数は概ね10~16ページ程度で安定しますが、60号では過去最高の22ページ、69号ではそれを上回る24ページ、更に100号では26ページを記録するなど、要所には前期には見られない巨大な会報が出現します。このため、中期は「巨大会報の時代」だといえます。また、内容については前期とは別の意味で多様性に富んだものになり、前期の「執筆者の時代」に対して中期は「読者の時代」とも言えるでしょう。 しかし、読者の時代は編集者にとっては苦難の時代でもあったようです。というのは、手書き時代と同等のページ数に戻るということは、逆に言えば文書量が手書き時代の3倍超になっていることでもあり、当時のOA機器の普及水準から考えると原稿は手書きが大半だったはずですので、その作業量は膨大なものであったに違いないからです。 実際、紙面においても度々「ワープロの打てる方」の支援が求められており、70号からは「持ちまわり」で編集を行うようになるなど、その様子が垣間見えます。我々がこの時代の会報を目にするとき、その裏には編集者の多大な苦労があることを忘れてはなりません。 さて、このようにして、ある意味黄金期を迎えた備陽史探訪に第2の変革の波が押し寄せます。渡来系用紙規格(A4サイズ)の導入です。この規格は103号から始まり現在まで続くもので、在地系規格(B5サイズ)の中期以前に比べ紙の面積が約1.3倍に拡大することになります。しかし、前期から中期への1度目の変革時と本質的に大きく異なっているのは、この面積の拡大が文字数の増加に使われるのではなく、文字サイズの拡大(9→10pt)という逆の方向に使われたことです。 では、2度目の変革はどうして1度目と方向性が異なったのでしょうか?その背景を探ると、1度目が編集側の積極的な意志が示されるのに対して、2度目は編集側の強い意志が読み取れないことが見えてきます。 というのは、読者にとっては2度目の変革(渡来系規格導入)は紙面の視認性を飛躍的に向上させるもので、外面的なインパクトとしては1度目(活字化)に匹敵するものですが、他方で編集側の観点からは2度目の変革は影響が極めて小規模なものなのです。やや逆説的になるのですが、1度目の変革には編集側に主体的な活動が求められますが、2度目は能動的な動きを必要とせず、それ以外の外的要因の働いた蓋然性が高いと推察できるのです。そして、当時の出版業界の情勢を鑑みれば渡来系文化(A版)普及の一端として2度目の変革が備陽史探訪に波及した可能性が浮かび上がってきます。このことは103号の編集後記に「ええ~い、国際社会をなんと心得おる、大きくしちゃえ」と記されるなど、文献からも裏付けられます。 言い換えるなら、1度目の変革が中からの変革であるのに対し、2度目の変革は外からの変革といえるでしょう。 こうした2度の変革を経て後期に入ると、備陽史探訪は円熟期ともいえる時期を迎えます。内容、ページ数、発行間隔も現在まで長期に安定しており、私はこの平和期を「パクス・ビヨウシーナ(備陽史探訪の平和)」と呼称することを提唱したいと思います。 以上、これまでの備陽史探訪を大きな流れで考察しましたが、前期過程の中で突発的に発生し消滅した備探通信など、まだまだ未解明な部分も多く今後の研究の進展が期待されます。 ※この記事はネタです。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会