馬屋原氏の盛衰(神石郡最大の国人・素性から居城まで)
「備陽史探訪:132号」より
田口 義之
馬屋原氏の素性
『西備名区』によると、戦国時代、神石郡最大の国人に成長した馬屋原氏は、保元の乱で敗死した平忠正の末子正友が源平の争乱で源氏に味方して備中国水越馬屋原郷を得たことに始まり、正友五世の孫貞宗は北条氏に随身し、本領の他に備後志麻利庄を獲得して庄内の上村(神石高原町大字上)に居住、備後馬屋原氏の祖となったという。
室町時代中期、志麻利庄は室町幕府の「御料所」となり、代官として伊勢氏が支配していた。康正二(一四五六)年、庄内父木野(三和町父木野)の段銭は、杉原美濃守が幕府に納めている。これら幕府御料所としての志麻利庄に関連する史料には馬屋原氏の名は一切現れない。
また、馬屋原氏の出自に関しては異説もある。「萩藩閥閲録』四一、馬屋原弥四郎家の家譜によると、同氏は、源義家の弟義綱が上総国馬屋原庄に居住したことに始まり、義綱十六代の子孫光忠が備後神石郡に下向し備後馬屋原氏の祖となったという。
馬屋原氏が源平いずれに出るかは別にして、鎌倉時代、志麻利庄の地頭として入部した関東御家人であったことは、後の同氏の勢力から考えて認めて良い。
馬屋原氏の登場

伊勢氏の志麻利荘支配は、全体ではなく、宮氏や杉原氏が支配した地域もあったと考えられるから、戦国時代以前の馬屋原氏は、伊勢氏や宮の下にあって在地に勢力を培っていたものと推定される。馬屋原氏の中には、平姓を称する者もあったから、あるいは在京武士である伊勢氏(平姓)の現地代官として同地に下向し、そのまま土着して豪族化した者かもしれない。
戦国時代の馬屋原氏は、志麻利荘上村(神石高原町)の有井城から小畑(同町)の九鬼山城に本拠を移した馬屋原氏(平姓)と、小畑の北に聳える固屋城を本拠とした馬屋原氏(源姓)の有力な二家があって、それぞれ天文年間の後半には備後の国衆として史料に登場する。
史料に現れるのは固屋城馬屋原氏の方が早く、天文十七年(一五四八)七月、馬屋原義俊は、毛利氏から神辺表(深安郡神辺町)へ出陣するよう要請を受けた(『萩藩閥閲録』巻七七)。当時、備後南部では神辺城をめぐって大内・尼子の激戦が続いており、馬屋原氏も大内方としてこの戦いに参加したのである。
一方、九鬼城の馬屋原信春も大内・毛利方に属し、天文二〇年十月、大内氏年寄衆より書状を受けた(『同』巻四一)。天文年間、三村(神石高原町福永)に進出した尼子方に対して、大内義隆は毛利元就に「志麻利口」に出陣するよう要請した(「萩藩譜録」山内治左衛門通久)。両馬屋原氏が大内・毛利の陣営に属したことによって、同氏の本拠志麻利荘は、大内方の拠点となった。
福永の戦い

先の「三村」の戦いの結果、高尾氏は大内・毛利方に降り、天文十七年二月十七日、大内義隆は、高尾中務大輔先知行分「福永三百貫」を田総(庄原市総領町)の田総元里に与えた。
高尾氏が大内方に転じたことによって、同氏の本拠福永は、尼子氏に対する大内方の最前線となった。天文二十一年(一五五三)四月、尼子晴久が将軍足利義輝から備後など八カ国の守護職に任命されると、尼子の勢力は再び中国山脈を越えて備後に南下した。備後の国人の中には庄原の山内首藤氏をはじめ尼子に味方する者も多く、同年八月にはその先鋒は高光(神石高原町)に達し、以後翌天文二十二年(一五五三)十二月、尼子氏の軍勢が撤退するまで、福永の泉山城や高尾城をめぐって、激しい攻防戦が繰り返された。この戦いには大内o毛利方として馬屋原氏も高尾氏の援軍として参加し、毛利氏も家臣の飯田四郎右衛門尉を城番として福永要害(泉山城のことと推定される)に入れるなどして、高尾氏を援助した(『萩藩閥閲録』巻四一、巻七七、巻一五二、『田総文書』など)。
馬屋原氏と毛利氏

神石郡最大の国人となった馬屋原氏も、この政策によって毛利氏の姻戚関係に組み込まれた国人の一人であった。馬屋原氏と毛利氏の姻戚関係は、元就の弟元綱の子と伝わる敷名元範を通じてのものであった。固屋城馬屋原氏の家譜(『萩藩閥閲録』巻四一馬屋原弥四郎)によると、馬屋原義政に実子がなく、弘治元年九月、「大江弘元公之六男相合左馬助元綱公御嫡男」元範を養子として迎えたという。ただし、この伝えには疑問が多い。元網の子として敷名元範が存在したことは確かだが、元範は元亀年間(一五七〇から一五七三)に入っても「敷名兵部太夫元範」として史料に現れ、馬屋原氏を相続した形跡はない(『萩藩閥閲録』巻九六等)。
それよりも、史料で確認されるのは九鬼城馬屋原氏との関係である。『萩藩閥閲録』巻四一馬屋原山三郎家文書によると、敷名元範の子少輔五郎が馬屋原信春の子宮寿の後見として馬屋原氏に入り、宮寿が早世したため馬屋原家を相続したとある。信春は弘治三年の傘連判状に備後の国人として署名しており、馬屋原氏の一族の中では最も有力であった。敷名少輔五郎が九鬼城馬屋原氏を相続したのは、永禄十一年(一五六八)のことで、毛利氏は同年二月七日、馬屋原少輔五郎に同氏の本領「志摩利庄三百五十貫、豊松四ケ村四百四十貫余」の地を安堵した。馬屋原少輔五郎は後に「兵部大輔」と称し、天正三年(一五七五)正月の備中手要害(岡山県川上町)の合戦で首二十八を取り、毛利氏の「首注文」に載せられている(『毛利家文書』三七五号)。
以後、馬屋原氏は慶長五年の関が原合戦後長州に移るまで、毛利氏旗下の国衆として活躍した。
地域史と山城

南北朝の内乱は、山城の発展の、一つのピークとなった。楠木正成や赤松円心の活躍は、山城の有用性を認めさせ、各地の武士団は争って山城を築いた。この時代の山城は純粋に戦術的なもので、高い山頂や断崖に臨む尾根が利用され、堀切や曲輪の築造が始まった。神石郡内でもこの時期の山城と目されるものが数ヶ所知られている。小野(旧油木町)の追畑城は成羽川に臨む断崖上に築かれた険阻な山城で、周囲に可耕地はなく、純粋に立て篭もるために築かれた山城である。上野(同)の八頭城も簡単な構造で目立った遺構はなく、伝承からも南北朝期の築城と目される。
安田(同)の高子山城も南北朝時代にさかのぼる可能性のある山城である。同城は、山頂を三重の空堀をめぐらせただけの単純な構造で、城主宇賀氏と永聖寺の開基伝承から見て、築城が相当古いことが想像される。
郡内の山城のほとんどは、室町時代後期から戦国時代にかけて築かれ、利用されたものである。小畑(旧三和町)の固屋城、九鬼城、福永(旧神石町)の高尾城、高光(同)の馬場城は国人の拠点として機能した山城で、曲輪・空堀などを備えた典型的な戦国期山城の姿をとどめている。
国人の居城以外で、現在も顕著な遺構を残しているのは小野の小野山城と、宗兼(旧油木町)の大床山城である。両城とも、戦国期山城の特徴である畝条竪堀群の遺構を残し、戦国時代の一時期、付近が緊張した戦場になったことを物語っている。上野の土居城も良く遺構を残す山城である。同城は、尾根の先端部を堀切で遮断し、階段状に曲輪を並べた典型的な戦国山城で、城下には城主の平時の居館である「土居」の地名も残っている。小野の平松城、新免(旧油木町)の木路田城、油木の土居城、仙養(同)の青山城は中世の館城の遺跡である。館城は鎌倉時代の方形居館が戦国期まで使用され、防備が強化されたもので、国人領主に成長できなかった在地領主が終始本拠として使用した。いずれにしても文字に記された記録が少ない地方では、山城跡は中世の歴史を探る重要な手掛かりとなる貴重な文化財である。
https://bingo-history.net/archives/12014https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/02/05c5844b91c969b37a83868aae31836c.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/02/05c5844b91c969b37a83868aae31836c-150x100.jpg中世史「備陽史探訪:132号」より 田口 義之 馬屋原氏の素性 『西備名区』によると、戦国時代、神石郡最大の国人に成長した馬屋原氏は、保元の乱で敗死した平忠正の末子正友が源平の争乱で源氏に味方して備中国水越馬屋原郷を得たことに始まり、正友五世の孫貞宗は北条氏に随身し、本領の他に備後志麻利庄を獲得して庄内の上村(神石高原町大字上)に居住、備後馬屋原氏の祖となったという。 室町時代中期、志麻利庄は室町幕府の「御料所」となり、代官として伊勢氏が支配していた。康正二(一四五六)年、庄内父木野(三和町父木野)の段銭は、杉原美濃守が幕府に納めている。これら幕府御料所としての志麻利庄に関連する史料には馬屋原氏の名は一切現れない。 また、馬屋原氏の出自に関しては異説もある。「萩藩閥閲録』四一、馬屋原弥四郎家の家譜によると、同氏は、源義家の弟義綱が上総国馬屋原庄に居住したことに始まり、義綱十六代の子孫光忠が備後神石郡に下向し備後馬屋原氏の祖となったという。 馬屋原氏が源平いずれに出るかは別にして、鎌倉時代、志麻利庄の地頭として入部した関東御家人であったことは、後の同氏の勢力から考えて認めて良い。 馬屋原氏の登場 馬屋原氏は、先に述べたように、鎌倉時代に志麻利荘の地頭として入部したと伝える東国武士であるが、戦国時代中期の天文年間に入って確実な史料に登場するまでは一切良質な資料に現れない。同氏の本拠とされる志麻利荘は、明応年間(一四九二~一五〇一)まで幕府の料所として見え(「前田家所蔵文書」)、代官として幕府政所執事伊勢氏の一族が支配していた(「康正二年造内裏段銭并国役引付」)。 伊勢氏の志麻利荘支配は、全体ではなく、宮氏や杉原氏が支配した地域もあったと考えられるから、戦国時代以前の馬屋原氏は、伊勢氏や宮の下にあって在地に勢力を培っていたものと推定される。馬屋原氏の中には、平姓を称する者もあったから、あるいは在京武士である伊勢氏(平姓)の現地代官として同地に下向し、そのまま土着して豪族化した者かもしれない。 戦国時代の馬屋原氏は、志麻利荘上村(神石高原町)の有井城から小畑(同町)の九鬼山城に本拠を移した馬屋原氏(平姓)と、小畑の北に聳える固屋城を本拠とした馬屋原氏(源姓)の有力な二家があって、それぞれ天文年間の後半には備後の国衆として史料に登場する。 史料に現れるのは固屋城馬屋原氏の方が早く、天文十七年(一五四八)七月、馬屋原義俊は、毛利氏から神辺表(深安郡神辺町)へ出陣するよう要請を受けた(『萩藩閥閲録』巻七七)。当時、備後南部では神辺城をめぐって大内・尼子の激戦が続いており、馬屋原氏も大内方としてこの戦いに参加したのである。 一方、九鬼城の馬屋原信春も大内・毛利方に属し、天文二〇年十月、大内氏年寄衆より書状を受けた(『同』巻四一)。天文年間、三村(神石高原町福永)に進出した尼子方に対して、大内義隆は毛利元就に「志麻利口」に出陣するよう要請した(「萩藩譜録」山内治左衛門通久)。両馬屋原氏が大内・毛利の陣営に属したことによって、同氏の本拠志麻利荘は、大内方の拠点となった。 福永の戦い 志麻利荘一帯が、大内方の拠点となったのに対し、北部の高光・福永一帯には尼子氏の勢力が侵入し、大内・毛利方と激しい戦いとなった。福永には、宮氏の一門高尾氏が本拠を置き、尼子方に属した。 先の「三村」の戦いの結果、高尾氏は大内・毛利方に降り、天文十七年二月十七日、大内義隆は、高尾中務大輔先知行分「福永三百貫」を田総(庄原市総領町)の田総元里に与えた。 高尾氏が大内方に転じたことによって、同氏の本拠福永は、尼子氏に対する大内方の最前線となった。天文二十一年(一五五三)四月、尼子晴久が将軍足利義輝から備後など八カ国の守護職に任命されると、尼子の勢力は再び中国山脈を越えて備後に南下した。備後の国人の中には庄原の山内首藤氏をはじめ尼子に味方する者も多く、同年八月にはその先鋒は高光(神石高原町)に達し、以後翌天文二十二年(一五五三)十二月、尼子氏の軍勢が撤退するまで、福永の泉山城や高尾城をめぐって、激しい攻防戦が繰り返された。この戦いには大内o毛利方として馬屋原氏も高尾氏の援軍として参加し、毛利氏も家臣の飯田四郎右衛門尉を城番として福永要害(泉山城のことと推定される)に入れるなどして、高尾氏を援助した(『萩藩閥閲録』巻四一、巻七七、巻一五二、『田総文書』など)。 馬屋原氏と毛利氏 毛利氏の備後支配は、各地の有力な国人と婚姻や養子縁組を結ぶことで強化された。元就の姪は御調の渋川義正の正妻となり、娘の一人は世羅郡の国人上原元将に入嫁した。元春の妻、熊谷氏の妹は、庄原の山内隆通の後妻となった。また、自身の後妻は三次の三吉致高の娘であった。元就は上原・山内・三吉などの有力国人と姻戚関係を結ぶことによって、毛利勢力の浸透を謀った。 神石郡最大の国人となった馬屋原氏も、この政策によって毛利氏の姻戚関係に組み込まれた国人の一人であった。馬屋原氏と毛利氏の姻戚関係は、元就の弟元綱の子と伝わる敷名元範を通じてのものであった。固屋城馬屋原氏の家譜(『萩藩閥閲録』巻四一馬屋原弥四郎)によると、馬屋原義政に実子がなく、弘治元年九月、「大江弘元公之六男相合左馬助元綱公御嫡男」元範を養子として迎えたという。ただし、この伝えには疑問が多い。元網の子として敷名元範が存在したことは確かだが、元範は元亀年間(一五七〇から一五七三)に入っても「敷名兵部太夫元範」として史料に現れ、馬屋原氏を相続した形跡はない(『萩藩閥閲録』巻九六等)。 それよりも、史料で確認されるのは九鬼城馬屋原氏との関係である。『萩藩閥閲録』巻四一馬屋原山三郎家文書によると、敷名元範の子少輔五郎が馬屋原信春の子宮寿の後見として馬屋原氏に入り、宮寿が早世したため馬屋原家を相続したとある。信春は弘治三年の傘連判状に備後の国人として署名しており、馬屋原氏の一族の中では最も有力であった。敷名少輔五郎が九鬼城馬屋原氏を相続したのは、永禄十一年(一五六八)のことで、毛利氏は同年二月七日、馬屋原少輔五郎に同氏の本領「志摩利庄三百五十貫、豊松四ケ村四百四十貫余」の地を安堵した。馬屋原少輔五郎は後に「兵部大輔」と称し、天正三年(一五七五)正月の備中手要害(岡山県川上町)の合戦で首二十八を取り、毛利氏の「首注文」に載せられている(『毛利家文書』三七五号)。 以後、馬屋原氏は慶長五年の関が原合戦後長州に移るまで、毛利氏旗下の国衆として活躍した。 地域史と山城 中世の山城は、土に根を張った国人・土豪が残したものである。中世山城の起源は鎌倉時代の在地領主の「館」に始まる。在地領主は自らの屋敷の廻りを土塁と掘で固め、背後の丘陵上に簡単な出城を築いた。当初は山頂に柵をめぐらし、粗末な矢倉を上げただけの簡単な構造で、今に残るような施設は何もなかった。 南北朝の内乱は、山城の発展の、一つのピークとなった。楠木正成や赤松円心の活躍は、山城の有用性を認めさせ、各地の武士団は争って山城を築いた。この時代の山城は純粋に戦術的なもので、高い山頂や断崖に臨む尾根が利用され、堀切や曲輪の築造が始まった。神石郡内でもこの時期の山城と目されるものが数ヶ所知られている。小野(旧油木町)の追畑城は成羽川に臨む断崖上に築かれた険阻な山城で、周囲に可耕地はなく、純粋に立て篭もるために築かれた山城である。上野(同)の八頭城も簡単な構造で目立った遺構はなく、伝承からも南北朝期の築城と目される。 安田(同)の高子山城も南北朝時代にさかのぼる可能性のある山城である。同城は、山頂を三重の空堀をめぐらせただけの単純な構造で、城主宇賀氏と永聖寺の開基伝承から見て、築城が相当古いことが想像される。 郡内の山城のほとんどは、室町時代後期から戦国時代にかけて築かれ、利用されたものである。小畑(旧三和町)の固屋城、九鬼城、福永(旧神石町)の高尾城、高光(同)の馬場城は国人の拠点として機能した山城で、曲輪・空堀などを備えた典型的な戦国期山城の姿をとどめている。 国人の居城以外で、現在も顕著な遺構を残しているのは小野の小野山城と、宗兼(旧油木町)の大床山城である。両城とも、戦国期山城の特徴である畝条竪堀群の遺構を残し、戦国時代の一時期、付近が緊張した戦場になったことを物語っている。上野の土居城も良く遺構を残す山城である。同城は、尾根の先端部を堀切で遮断し、階段状に曲輪を並べた典型的な戦国山城で、城下には城主の平時の居館である「土居」の地名も残っている。小野の平松城、新免(旧油木町)の木路田城、油木の土居城、仙養(同)の青山城は中世の館城の遺跡である。館城は鎌倉時代の方形居館が戦国期まで使用され、防備が強化されたもので、国人領主に成長できなかった在地領主が終始本拠として使用した。いずれにしても文字に記された記録が少ない地方では、山城跡は中世の歴史を探る重要な手掛かりとなる貴重な文化財である。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会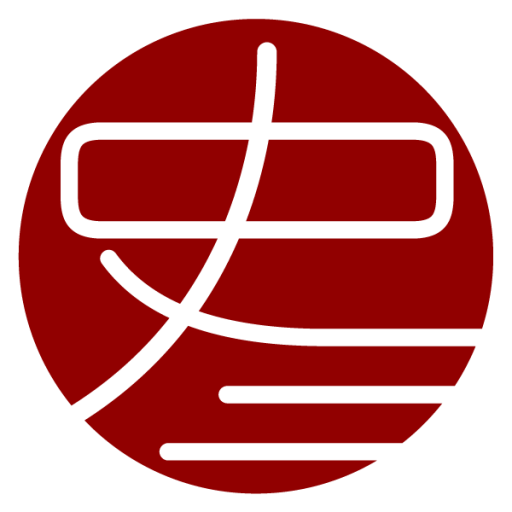
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 中世を読む




