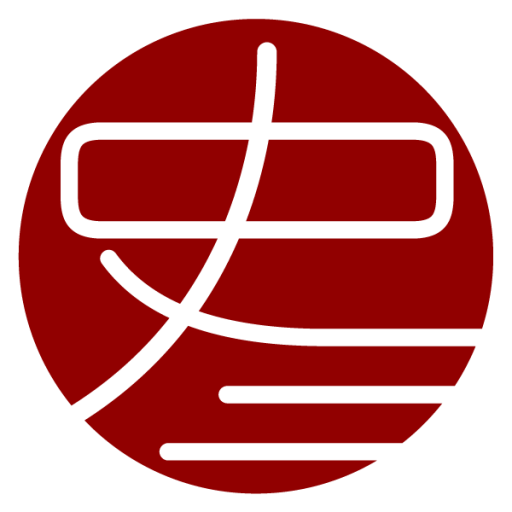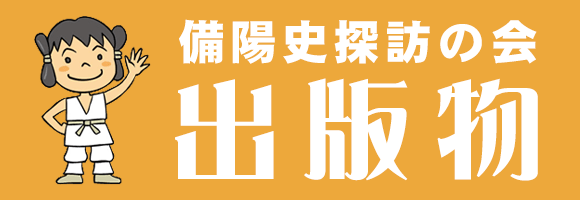「備陽史探訪:27号」より
高橋 義視
二月の例会で登った蔵王山の北北東約八〇〇米、国道一八二号線を跨いだ小高い山の中腹に由緒ありげな古寺のたたずまいがある。
数年前、千田町に転居した私は足の赴くまま附近を、よく散策する。
そうしたある朝、私は国道からそれた参道入口にたつ左右一対の大きな石灯篭の間を通り抜けて、勾配四〇度はあらうかと思える急坂をのぼって行った。
一五〇米程のぼった所の曲り角に小さな首無不動尊が祀られていて中年の婦人が清掃していた。挨拶を交わして更に道を右手に行くと二階建て式の山門がある。
「賓壽院」と書いた大きな横額が掲げられている。建築様式から、かなり古い年代のものであることが窺える。
門を這入ると本堂(大悲殿)と庫裏が並んで建っている。庫裏は古びた感じだが、本堂や境内の土塀、それに山門の一部は最近修復工事がされたらしい。
庫裏には人の気配が全くなく軒先の一隅に高さ八〇センチメートル程の緑青の朽ちた半鐘がぶらさがっている。
半鐘の上にのせてある木槌を取って三回打ってみた「仏・法・僧」えの畏敬をこめて……
静かな境内に、ふと人の気配がして一人の老人が門を這入って来た。
人の好きそうなその老人は軽く会釈して私の前を通りすぎ「大悲殿」の大額がかかっている本堂の前に額づき、合掌して敬虔なお祈りを捧げた。
私はその古老から、この寺の由来や、庫裏の軒先に吊るしてある半鐘が紛失した事件など聞かせて貰うことができた。
古老の話によると、この古刹は新宮寺といい、約八〇〇年前の元享八年に全国を修業行脚していた歡快僧正がこの地に到り開基したものであると寺に伝わる古文書に記されているそうであり、この地方の豪族や民衆の信仰の據りどころとして、あがめられた。
後世、本地垂迹説に基づく神仏混淆の風潮のなかで、新宮寺の裏山に八幡宮が造営されるに及んで、神宮寺が八幡宮の別当となり、神祇神事一切を新宮寺僧侶が取り仕切り、寺院の権勢は大いに高まった。
近世に至り無住職の寺となり、神社と共に廃れた時期もあったが、往時に於いては寺の規模といい、建物の構築様式といい、備後一円では、有数の寺院であった由である。
建物の構築様式といえば、山門の上に鐘楼があるというも珍しい。
梵鐘は戦時中に徴発されて今日その音色を聞くことはできない。
さて、半鐘の一件であるが、去る昭和五十一年(一九七六年)九月福山地方を襲った颱風のため庫裏は全壊し、本堂及び山門、土塀など半壊するという被害に遭い、その取り片付けが一段落した十月、半鐘が行方不明になっているのが判った。
神宮寺では八方手をつくして捜査したが遂に発見することが出来なかった。寺宝類は殆ど無事だったのに半鐘だけ失って残念なことだと諦めていたところ、七年後の昭和五十八年(一九八三年)十月、九州市内の古美術商から福山市教育委員会へ半鐘についての問い合わせがあり、市教委が関係寺院に諮問した結果、神宮寺のものが盗難に会ったことが判明した。
古美術商の話では、「最近この鐘を入手したが鐘に刻まれている銘文から寺の大切な品物であろうと推察され他への転買も憚られるので、お返ししたい」ということで、神宮寺が買い戻したが、その際、先方の商人が所用を兼ねてとは言いながら福山まで持参して下さったことに深く感謝しているとのことであった。
因みに鐘には次のような銘文が刻まれている。
奉寄附喚鐘一口為
備之後州探津郡千
田邑八幅山神宮寺
阿弥陀院什物
伏祈宗心信士妙光
信尼六親并十万舎
霊成三菩提也
享保十六年亥九月吉日
願主 沙門胎蓮
施主 福山住人
宗仙
そのあと、老人は私に、この寺から南に尾根づたいに行かれると古い塚や墓石、石棺など多くあると教えてくれたが、陽も大ぶん高くなり、またの機会に散策したいと思いつつ、老人に謝辞をのべて神宮寺から離れた。
【宝寿院神宮寺】
https://bingo-history.net/archives/30410https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2017/09/cropped-mark.pnghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2017/09/cropped-mark-150x100.png管理人中世史近世近代史「備陽史探訪:27号」より
高橋 義視
二月の例会で登った蔵王山の北北東約八〇〇米、国道一八二号線を跨いだ小高い山の中腹に由緒ありげな古寺のたたずまいがある。
数年前、千田町に転居した私は足の赴くまま附近を、よく散策する。
そうしたある朝、私は国道からそれた参道入口にたつ左右一対の大きな石灯篭の間を通り抜けて、勾配四〇度はあらうかと思える急坂をのぼって行った。
一五〇米程のぼった所の曲り角に小さな首無不動尊が祀られていて中年の婦人が清掃していた。挨拶を交わして更に道を右手に行くと二階建て式の山門がある。
「賓壽院」と書いた大きな横額が掲げられている。建築様式から、かなり古い年代のものであることが窺える。
門を這入ると本堂(大悲殿)と庫裏が並んで建っている。庫裏は古びた感じだが、本堂や境内の土塀、それに山門の一部は最近修復工事がされたらしい。
庫裏には人の気配が全くなく軒先の一隅に高さ八〇センチメートル程の緑青の朽ちた半鐘がぶらさがっている。
半鐘の上にのせてある木槌を取って三回打ってみた「仏・法・僧」えの畏敬をこめて……
静かな境内に、ふと人の気配がして一人の老人が門を這入って来た。
人の好きそうなその老人は軽く会釈して私の前を通りすぎ「大悲殿」の大額がかかっている本堂の前に額づき、合掌して敬虔なお祈りを捧げた。
私はその古老から、この寺の由来や、庫裏の軒先に吊るしてある半鐘が紛失した事件など聞かせて貰うことができた。
古老の話によると、この古刹は新宮寺といい、約八〇〇年前の元享八年に全国を修業行脚していた歡快僧正がこの地に到り開基したものであると寺に伝わる古文書に記されているそうであり、この地方の豪族や民衆の信仰の據りどころとして、あがめられた。
後世、本地垂迹説に基づく神仏混淆の風潮のなかで、新宮寺の裏山に八幡宮が造営されるに及んで、神宮寺が八幡宮の別当となり、神祇神事一切を新宮寺僧侶が取り仕切り、寺院の権勢は大いに高まった。
近世に至り無住職の寺となり、神社と共に廃れた時期もあったが、往時に於いては寺の規模といい、建物の構築様式といい、備後一円では、有数の寺院であった由である。
建物の構築様式といえば、山門の上に鐘楼があるというも珍しい。
梵鐘は戦時中に徴発されて今日その音色を聞くことはできない。
さて、半鐘の一件であるが、去る昭和五十一年(一九七六年)九月福山地方を襲った颱風のため庫裏は全壊し、本堂及び山門、土塀など半壊するという被害に遭い、その取り片付けが一段落した十月、半鐘が行方不明になっているのが判った。
神宮寺では八方手をつくして捜査したが遂に発見することが出来なかった。寺宝類は殆ど無事だったのに半鐘だけ失って残念なことだと諦めていたところ、七年後の昭和五十八年(一九八三年)十月、九州市内の古美術商から福山市教育委員会へ半鐘についての問い合わせがあり、市教委が関係寺院に諮問した結果、神宮寺のものが盗難に会ったことが判明した。
古美術商の話では、「最近この鐘を入手したが鐘に刻まれている銘文から寺の大切な品物であろうと推察され他への転買も憚られるので、お返ししたい」ということで、神宮寺が買い戻したが、その際、先方の商人が所用を兼ねてとは言いながら福山まで持参して下さったことに深く感謝しているとのことであった。
因みに鐘には次のような銘文が刻まれている。
奉寄附喚鐘一口為
備之後州探津郡千
田邑八幅山神宮寺
阿弥陀院什物
伏祈宗心信士妙光
信尼六親并十万舎
霊成三菩提也
享保十六年亥九月吉日
願主 沙門胎蓮
施主 福山住人
宗仙
そのあと、老人は私に、この寺から南に尾根づたいに行かれると古い塚や墓石、石棺など多くあると教えてくれたが、陽も大ぶん高くなり、またの機会に散策したいと思いつつ、老人に謝辞をのべて神宮寺から離れた。 【宝寿院神宮寺】管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
中世を読む
備陽史探訪の会近世近代史部会では「近世福山の歴史を学ぶ」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
近世福山の歴史を学ぶ