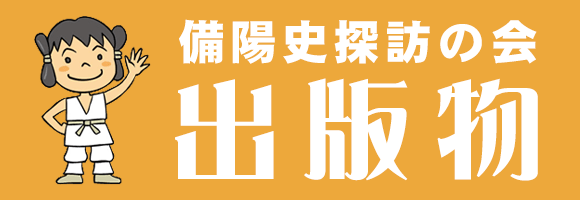1月18日 中世を読む【現地学習】「円寿寺山城と海裹庄」開催
中世を読む(403)
【現地学習】備後の城館「円寿寺山城と海裹庄」
https://bingo-history.net/archives/29641https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2025/02/1739968424601-1024x768.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2025/02/1739968424601-150x100.jpg活動報告中世を読む(403) 【現地学習】備後の城館「円寿寺山城と海裹庄」行事管理行事管理 jimu@bingo-history.netAuthor備陽史探訪の会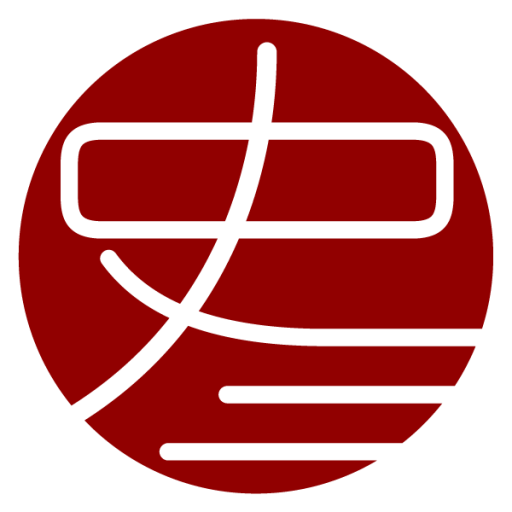

広島県世羅郡世羅町宇津戸
中世には海裹庄とよばれた宇津戸地域の庄園の名残りと城跡を城郭研究をされている谷本寛先生に案内してもらいました。
照善寺に集合し行程の説明です。

まずは、毛利秀包の城と伝わる円寿寺山城へと…
主要部の曲輪跡周辺は雑木が生い茂る状態ではありましたが、切岸や土塁状の地形が明瞭です。
谷本先生の「皆さんどう考える?」の逆質問に、戸惑いながらも参加者の皆さん意見を返されてました。

次に訪れたのは、領家八幡神社
ここでの解説は、飛び入りで参加した世羅町教育委員会の林氏
庄園の中分の名残りが今もしっかりと残っています。

山伝城では丘陵上の主曲輪群と先端部に位置する出丸とされる遺構をみてまわりました。
出丸からは、宇津戸が一望でき「あそこからこっちが地頭方で…」と中分の境界もわかりやすく確認できます。

地頭八幡神社では、林氏から天正12年の棟札の銘文の中に毛利元就の末息子である毛利元総(のちの秀包)の名が記されているとの説明がありました。

最後に世羅町宇津戸自治センターにておひらき
谷本先生 林さん ありがとうございました。