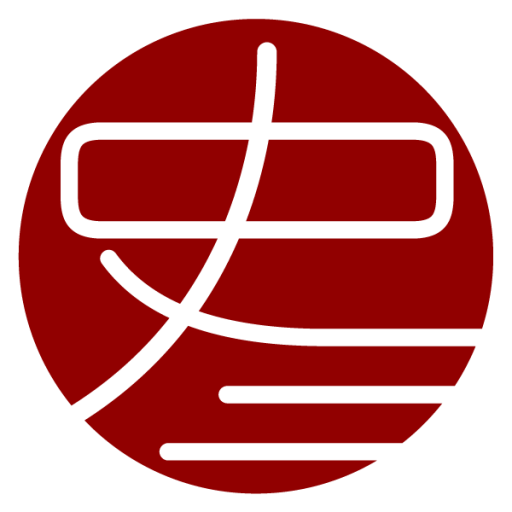神辺平野の北縁は、吉備高原の山波が急傾斜で平野部に落ち込み、高原に水源を持つ小河川によって侵食された幾つもの谷筋によって形成されている。戦国時代、備後宮氏と安芸毛利氏の雌雄を懸けた決戦が行われた志川滝山城は、こうした吉備高原から流れ出た小河川の一つ、加茂川流域に開けた加茂町の平野から、更に西に分かれた同町四川の谷合の一番奥まった所に位置する。
城は、この四川谷の最奥部の、谷筋を二分するように東南に突出した標高三九二メートルの尾根を大規模な堀切によって独立させ、その東の山頂部を削平して山城としたもので、地理的には神辺平野の中心部からは隔絶した位置にあるが、山頂部からは南側の山波越しに神辺から更に福山方面を見通すことが出来、「備後外郡」と呼ばれた備後の山間部から備後南部の平野部への進出拠点としては絶好の位置を占めている。
山城としての志川滝山城は、地形によって大きく東西二つの部分に分かれる。後世の本丸に当たるのは西側の曲輪群で、標高三九二メートルの山頂を削平して南北一〇〇メートルに達する長大な曲輪を築き、更にそれを守るように周囲に一段切り下げて幅五~一〇メートルの帯曲輪をめぐらせている。山頂からは鞍部を隔てて東方に尾根が突出し、この部分に東側の曲輪群が設けられている。その中心は尾根上を削平した、東西約八〇メートルの曲輪で、幅最大一〇メートルを測り、東に二段の腰曲輪、西端には長径一八メートルの櫓台を築き、防備を固めている。
以上の城郭要部を守るために築かれたのが、西側に続く尾根筋を断ち切った大堀切である。ただし、加工の痕跡はそれほど明瞭ではなく、この城の唯一つの弱点となっており、後に述べるように天文二一年七月の合戦で毛利勢が攻め寄せたのもこの方面からであった。なお、堀切は東側曲輪群と西側曲輪群を隔てる鞍部にも認められるが、加工の度合いは低く、曲輪の切岸が不明瞭な点と相俟って、全体的に未完成の印象を与える。このこともこれだけの天険を擁しながら城側があっけなく敗れた要因の一つであろう。 『西備名区』等の郷土史書によると、この地に初めて城を築いたのは、山野の戸屋ケ丸城にいた宮三郎義兼という者で、明応元年(一四六二)のこととしている。しかし、この城を一躍有名にしたのは、言うまでもなく、この地が天文二一年(一五五二)七月の所謂「志川滝山合戦」の舞台となったからである。
志川滝山合戦は、南北朝時代以来、備南に勢力を持った宮氏と、安芸の毛利氏とが神辺平野の覇権をめぐって争った戦いで、これを大きな視野でとらえれば、出雲の戦国大名尼子氏と、大内義隆を殺し、大内氏の実権を握った陶氏、及びその与党の毛利氏が、備後南部の支配権をめぐって争った一連の合戦の一部である。すなわち、天文一八年(一五四九)九月の神辺城の陥落によって備後南部の足場を失った尼子氏は、天文二一年(一五五二)四月、将軍義輝より備後など八ケ国の守護職を与えられると、再び中国山脈を越えて南下の姿勢を示し、これに同じく毛利氏の圧迫によって備南での地位を失いつつあった宮氏が、入道光音を盟主に応じ、この合戦となったものである。

その初動は、同年六月には始まっていたようである。同月七日、陶晴賢は芸備の国人衆に充てて、「備後境目動之儀」について、江良丹後守を上使として派遣したから、元就と相談して出兵するよう指令を発している(閥閲録一〇四)。「備後境目」とは国境の意ではなく、強敵尼子氏の勢力圏との接点を指していることは言うまでもない。そして、翌七月、備後に出兵した毛利元就は、同月二十三日、一気に総攻撃を決行して、宮氏の籠る当城を落とした。当日の城攻めは、城の「尾首」、すなわち、先に述べた当城の弱点、西方尾根続きから行われたようで、元就が家臣に与えた感状にも「尾首構際に至り」という言葉が見られる(閥閲録一二八等)。しかし、毛利方も二二六人に達する戦死傷者を出しており、城方の抵抗もかなり激しかったことを窺わせる(毛利家文書二九三号等)。
城跡を訪ねるには、バス利用だと井笠バスの山野・加茂方面行きに乗車し、「四川別れ」で下車する。ここからは自分の足が頼りである。四川の谷を登って行くと、前方に険しい山肌を見せる山が迫って来る。これが志川滝山城跡である。正面からの登りは危険で、一旦突き当たりの大谷池の土手へ出て、西方から城跡を目指す。
【志川滝山城跡】
《参考文献》
新人物往来社刊「日本城郭体系」
広島・岡山 芸備友の会「広島県の主要城跡」
田口義之「志川滝山合戦について」文化財ふくやま一七号
https://bingo-history.net/archives/1596https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/06-1.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/06-1-150x150.jpg管理人中世史山城,解説神辺平野の北縁は、吉備高原の山波が急傾斜で平野部に落ち込み、高原に水源を持つ小河川によって侵食された幾つもの谷筋によって形成されている。戦国時代、備後宮氏と安芸毛利氏の雌雄を懸けた決戦が行われた志川滝山城は、こうした吉備高原から流れ出た小河川の一つ、加茂川流域に開けた加茂町の平野から、更に西に分かれた同町四川の谷合の一番奥まった所に位置する。 城は、この四川谷の最奥部の、谷筋を二分するように東南に突出した標高三九二メートルの尾根を大規模な堀切によって独立させ、その東の山頂部を削平して山城としたもので、地理的には神辺平野の中心部からは隔絶した位置にあるが、山頂部からは南側の山波越しに神辺から更に福山方面を見通すことが出来、「備後外郡」と呼ばれた備後の山間部から備後南部の平野部への進出拠点としては絶好の位置を占めている。 山城としての志川滝山城は、地形によって大きく東西二つの部分に分かれる。後世の本丸に当たるのは西側の曲輪群で、標高三九二メートルの山頂を削平して南北一〇〇メートルに達する長大な曲輪を築き、更にそれを守るように周囲に一段切り下げて幅五~一〇メートルの帯曲輪をめぐらせている。山頂からは鞍部を隔てて東方に尾根が突出し、この部分に東側の曲輪群が設けられている。その中心は尾根上を削平した、東西約八〇メートルの曲輪で、幅最大一〇メートルを測り、東に二段の腰曲輪、西端には長径一八メートルの櫓台を築き、防備を固めている。 以上の城郭要部を守るために築かれたのが、西側に続く尾根筋を断ち切った大堀切である。ただし、加工の痕跡はそれほど明瞭ではなく、この城の唯一つの弱点となっており、後に述べるように天文二一年七月の合戦で毛利勢が攻め寄せたのもこの方面からであった。なお、堀切は東側曲輪群と西側曲輪群を隔てる鞍部にも認められるが、加工の度合いは低く、曲輪の切岸が不明瞭な点と相俟って、全体的に未完成の印象を与える。このこともこれだけの天険を擁しながら城側があっけなく敗れた要因の一つであろう。 『西備名区』等の郷土史書によると、この地に初めて城を築いたのは、山野の戸屋ケ丸城にいた宮三郎義兼という者で、明応元年(一四六二)のこととしている。しかし、この城を一躍有名にしたのは、言うまでもなく、この地が天文二一年(一五五二)七月の所謂「志川滝山合戦」の舞台となったからである。 志川滝山合戦は、南北朝時代以来、備南に勢力を持った宮氏と、安芸の毛利氏とが神辺平野の覇権をめぐって争った戦いで、これを大きな視野でとらえれば、出雲の戦国大名尼子氏と、大内義隆を殺し、大内氏の実権を握った陶氏、及びその与党の毛利氏が、備後南部の支配権をめぐって争った一連の合戦の一部である。すなわち、天文一八年(一五四九)九月の神辺城の陥落によって備後南部の足場を失った尼子氏は、天文二一年(一五五二)四月、将軍義輝より備後など八ケ国の守護職を与えられると、再び中国山脈を越えて南下の姿勢を示し、これに同じく毛利氏の圧迫によって備南での地位を失いつつあった宮氏が、入道光音を盟主に応じ、この合戦となったものである。 その初動は、同年六月には始まっていたようである。同月七日、陶晴賢は芸備の国人衆に充てて、「備後境目動之儀」について、江良丹後守を上使として派遣したから、元就と相談して出兵するよう指令を発している(閥閲録一〇四)。「備後境目」とは国境の意ではなく、強敵尼子氏の勢力圏との接点を指していることは言うまでもない。そして、翌七月、備後に出兵した毛利元就は、同月二十三日、一気に総攻撃を決行して、宮氏の籠る当城を落とした。当日の城攻めは、城の「尾首」、すなわち、先に述べた当城の弱点、西方尾根続きから行われたようで、元就が家臣に与えた感状にも「尾首構際に至り」という言葉が見られる(閥閲録一二八等)。しかし、毛利方も二二六人に達する戦死傷者を出しており、城方の抵抗もかなり激しかったことを窺わせる(毛利家文書二九三号等)。 城跡を訪ねるには、バス利用だと井笠バスの山野・加茂方面行きに乗車し、「四川別れ」で下車する。ここからは自分の足が頼りである。四川の谷を登って行くと、前方に険しい山肌を見せる山が迫って来る。これが志川滝山城跡である。正面からの登りは危険で、一旦突き当たりの大谷池の土手へ出て、西方から城跡を目指す。 【志川滝山城跡】
《参考文献》
新人物往来社刊「日本城郭体系」
広島・岡山 芸備友の会「広島県の主要城跡」
田口義之「志川滝山合戦について」文化財ふくやま一七号管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
中世を読む