幻の古代豪族(中世に活躍する安那氏・紀氏の末裔)
「備陽史探訪:119号」より
田口 義之
中世武士と近世の侍
中世は武士の時代である。武士と言うと、我々は江戸時代の侍をイメージする。ちょんまげを結い、大小の刀を腰に差し、裃を着てお城に出仕する。住まいは城下町にあり、藩より定期的に禄米を頂戴し、基本的に地方の農村に出かけることはない。
だが、平安の末に世の中の主役として登場した中世武士は違う。彼等の住まいは草深い農村の中にあり、平時は、農民と共に農業にいそしんだ。とうよりも、農民の中の有力者が武士であったと言うほうが分かりやすいかもしれない。
彼等の住居は水をたたえた堀に囲まれ、その内側には高い土手をめぐらせていた。土塁だ。土塁は当時「土居」と呼ばれ、彼等の住まいそのものを「土居」と呼んだ。今日でも各地に「土井」とか「でい」と呼ばれる場所があるが、それは彼等中世武士の屋敷跡であることが多い。
今、こころみにそうした場所に立ち、周囲を眺めてみよう。すると、一つの顕著な事実に気付く。それは、その場所が村一番の地味豊かな「田」であることである。つまり、武士というのは元々農民であって、その有力者に過ぎなかった、ということをこれらの事実は示している。
なるほど、近世の大名や武士の系図を見ると、麗々しく清和源氏の出であるとか、先祖は藤原氏の某であるとか記されている。だが、それはほとんどこじつけである。武士が天下を取り、支配者としての権威を身につけるために系図を飾ったに過ぎない。有名な話では今話題の徳川氏がそうだ。江戸時代に作られた徳川将軍家の系図を開くと、先祖は清和源氏の名門の出であり、我々は取るべくして天下を取ったのだと述べてある。しかし、これは真っ赤な偽りである。家康ははじめ藤原家康と署名しているし、徳川の系図は家康の依頼で京都の公家が「鼻紙」に書き写した某家の系図が元になって捏造されたものであることが、今では明らかになっている。
こうした江戸時代に作られた「系図」は、我々が知りたい中世武士の世界を間の彼方に追いやってしまった。土から離れた江戸時代の侍は、土にまみれた先祖の様子を自分の手で消し去ってしまったのである。
根強い古代豪族の生命力
草深い農村から生まれた武士の世界を思うとき、忘れてならないのは、古代豪族と中世武士の関連性である。古代の豪族は中世の開幕と共に消え去ったのであろうか。そんなことはありえない。
たとえば、古墳時代の吉備穴国造の系譜を引くと考えられる「安那氏」がいる。穴国造は旧安那郡(深安郡神辺町から福山市東北部にかけての地域)に勢力を持った古代豪族で、神辺平野東北部の巨大な古墳は彼等の墳墓と考えられている。安那氏のことは平安時代の文献にも登場し、古墳時代以来勢力を維持していたことが知られるが、御調八幡神社所蔵の版木によれば、鎌倉時代の嘉禎二年(一二三六)に至っても「安那定親」なる人物の活躍が知られるのである。
また、古代の大豪族「紀氏」も古代から中世にかけて福山地方で活躍した古代豪族の一人である。
紀氏の活躍は意外なところに痕跡を残していた。一つは平安時代の説話文学の代表例として知られる『今昔物語』である。面白いのですこし紹介してみよう。
今は昔、大蔵大夫紀助延という人があった。その助延が備後国に用事があって滞在していた時の話である。助延の家来が海岸で亀を見つけて遊んでいると、一人の家来がふざけて、『そいつは逃げた俺の女房だ。ここにいたのか』と言って、亀の口にキスをしようとした。ところが首をすぼめていた亀は突然首をのばし、その家来の口に噛みついた。引き離そうとしても、どうしても放さない…
(『今昔物語』巻二十九本朝付世俗大蔵大夫紀助延の郎党唇を亀に食はるる語第三十三)
説話はその様子を面白おかしく描写し、男の間抜けさを強調しているわけだが、ここで注目したいのは、口を亀に噛まれた男ではなく、備後国に用事があってやってきたという紀助延という人物のことである。
実は、紀氏に関しては福山には二つの注目すべき記録が発見されている。一つは、蔵王町の国史跡宮の前廃寺跡から出土した文字瓦である。宮の前廃寺跡は奈良時代に創建された海蔵寺の遺跡と言われ、数次の発掘によっておびただしい古代瓦が出土したが、その中に「紀臣和古女」「紀臣石女」と刻まれた瓦が発見されたのである。これで奈良時代福山湾岸に紀氏が勢力を持っていたことが判明した。さらに注目されるのは国宝の寺明王院の解体修理で発見された本堂内陣の墨書銘である。予想もされなかったことだが現明王院の本堂は鎌倉時代末期の元応三年(一三二一)、「紀貞経代々二世」の力によって建てられたことが判明したのである。
この二つの資料だけでは鎌倉末期の紀貞経が奈良時代の紀氏の後裔であると即断はできない。が、これに先ほどの『今昔物語』の紀助延を加えるとどうだろう。奈良・平安・鎌倉と紀氏の活躍が連綿と続いているわけで、これはどうしても福山湾岸に紀氏が古代以来勢力を持っていたと考えるほかない。しかし、紀氏の存在を伝える近世の記録は皆無である。これはどうしたことであろうか。紀氏は長い戦乱の中で滅んでいったのであろうか。勿論、それも考えられる。だが、江戸時代の作為された大量の系図群を見ると、それよりも同氏の一族は姓を「源平藤橘」に替え、姿を変えて生き延びていったとした方が良い。
宮氏の素性
たとえば、室町時代から戦国時代にかけて備後最大の勢力を誇った宮氏である。同氏の主流は戦国の荒波の中で毛利氏と対立し、敗れて滅んでいったが、今まで藤原摂関家の一人平安中期に活躍した関白小野宮実頼の後裔とばかり考えられていた。室町期の宮氏は皆「藤原」を称しており、戦国初頭の宮氏の画像の賛文に「小野宮四海の政に接し、聖化を翼賛す。居士以ってその苗裔たり」とあって、宮氏自身それを称していたことがわかる。
ところが、先年発刊された『東城町史』で驚くべき事実が明らかにされた。『庶軒日録』という室町時代の禅僧の日記に「奴可入道西寂は備後の宮の先祖なり…」と記されていたのだ。このことは近世の系図記録には一切記されていない。
奴可入道は、『平家物語』に出てくる河野氏によって討ち取られた奴可入道である。奴可は旧郡名(現比婆郡東半)だから、入道は古代以来の豪族の後裔であろう。入道西寂の活躍を室町時代の宮氏の人々が知らなかったはずはない。では、なぜ宮氏は入道が自分たちの先祖であると言わなかったのか。おそらくそれは『平家物語』に登場する入道の最後が余リカッコのいいものではなく、宮氏がそれを公言するのがはばかられるものだったからに違いない。
つまり、支配者となった武士は先祖をありのままに受け入れるのではなく、『選んだ』のである。こうして、本来の先祖は忘れられ、武士に『人気のある』源氏や平家、藤原氏が彼等の先祖になった。我々は、こうした捏造された系図や記録に惑わされることなく、現地に残る遺跡や同時代の史料に基づいて、郷土史を再構築しなければならない。
https://bingo-history.net/archives/11854https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/03/1a86d483764dec6e162dcb11ec421109.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/03/1a86d483764dec6e162dcb11ec421109-150x100.jpg中世史古代史「備陽史探訪:119号」より 田口 義之 中世武士と近世の侍 中世は武士の時代である。武士と言うと、我々は江戸時代の侍をイメージする。ちょんまげを結い、大小の刀を腰に差し、裃を着てお城に出仕する。住まいは城下町にあり、藩より定期的に禄米を頂戴し、基本的に地方の農村に出かけることはない。 だが、平安の末に世の中の主役として登場した中世武士は違う。彼等の住まいは草深い農村の中にあり、平時は、農民と共に農業にいそしんだ。とうよりも、農民の中の有力者が武士であったと言うほうが分かりやすいかもしれない。 彼等の住居は水をたたえた堀に囲まれ、その内側には高い土手をめぐらせていた。土塁だ。土塁は当時「土居」と呼ばれ、彼等の住まいそのものを「土居」と呼んだ。今日でも各地に「土井」とか「でい」と呼ばれる場所があるが、それは彼等中世武士の屋敷跡であることが多い。 今、こころみにそうした場所に立ち、周囲を眺めてみよう。すると、一つの顕著な事実に気付く。それは、その場所が村一番の地味豊かな「田」であることである。つまり、武士というのは元々農民であって、その有力者に過ぎなかった、ということをこれらの事実は示している。 なるほど、近世の大名や武士の系図を見ると、麗々しく清和源氏の出であるとか、先祖は藤原氏の某であるとか記されている。だが、それはほとんどこじつけである。武士が天下を取り、支配者としての権威を身につけるために系図を飾ったに過ぎない。有名な話では今話題の徳川氏がそうだ。江戸時代に作られた徳川将軍家の系図を開くと、先祖は清和源氏の名門の出であり、我々は取るべくして天下を取ったのだと述べてある。しかし、これは真っ赤な偽りである。家康ははじめ藤原家康と署名しているし、徳川の系図は家康の依頼で京都の公家が「鼻紙」に書き写した某家の系図が元になって捏造されたものであることが、今では明らかになっている。 こうした江戸時代に作られた「系図」は、我々が知りたい中世武士の世界を間の彼方に追いやってしまった。土から離れた江戸時代の侍は、土にまみれた先祖の様子を自分の手で消し去ってしまったのである。 根強い古代豪族の生命力 草深い農村から生まれた武士の世界を思うとき、忘れてならないのは、古代豪族と中世武士の関連性である。古代の豪族は中世の開幕と共に消え去ったのであろうか。そんなことはありえない。 たとえば、古墳時代の吉備穴国造の系譜を引くと考えられる「安那氏」がいる。穴国造は旧安那郡(深安郡神辺町から福山市東北部にかけての地域)に勢力を持った古代豪族で、神辺平野東北部の巨大な古墳は彼等の墳墓と考えられている。安那氏のことは平安時代の文献にも登場し、古墳時代以来勢力を維持していたことが知られるが、御調八幡神社所蔵の版木によれば、鎌倉時代の嘉禎二年(一二三六)に至っても「安那定親」なる人物の活躍が知られるのである。 また、古代の大豪族「紀氏」も古代から中世にかけて福山地方で活躍した古代豪族の一人である。 紀氏の活躍は意外なところに痕跡を残していた。一つは平安時代の説話文学の代表例として知られる『今昔物語』である。面白いのですこし紹介してみよう。 今は昔、大蔵大夫紀助延という人があった。その助延が備後国に用事があって滞在していた時の話である。助延の家来が海岸で亀を見つけて遊んでいると、一人の家来がふざけて、『そいつは逃げた俺の女房だ。ここにいたのか』と言って、亀の口にキスをしようとした。ところが首をすぼめていた亀は突然首をのばし、その家来の口に噛みついた。引き離そうとしても、どうしても放さない… (『今昔物語』巻二十九本朝付世俗大蔵大夫紀助延の郎党唇を亀に食はるる語第三十三) 説話はその様子を面白おかしく描写し、男の間抜けさを強調しているわけだが、ここで注目したいのは、口を亀に噛まれた男ではなく、備後国に用事があってやってきたという紀助延という人物のことである。 実は、紀氏に関しては福山には二つの注目すべき記録が発見されている。一つは、蔵王町の国史跡宮の前廃寺跡から出土した文字瓦である。宮の前廃寺跡は奈良時代に創建された海蔵寺の遺跡と言われ、数次の発掘によっておびただしい古代瓦が出土したが、その中に「紀臣和古女」「紀臣石女」と刻まれた瓦が発見されたのである。これで奈良時代福山湾岸に紀氏が勢力を持っていたことが判明した。さらに注目されるのは国宝の寺明王院の解体修理で発見された本堂内陣の墨書銘である。予想もされなかったことだが現明王院の本堂は鎌倉時代末期の元応三年(一三二一)、「紀貞経代々二世」の力によって建てられたことが判明したのである。 この二つの資料だけでは鎌倉末期の紀貞経が奈良時代の紀氏の後裔であると即断はできない。が、これに先ほどの『今昔物語』の紀助延を加えるとどうだろう。奈良・平安・鎌倉と紀氏の活躍が連綿と続いているわけで、これはどうしても福山湾岸に紀氏が古代以来勢力を持っていたと考えるほかない。しかし、紀氏の存在を伝える近世の記録は皆無である。これはどうしたことであろうか。紀氏は長い戦乱の中で滅んでいったのであろうか。勿論、それも考えられる。だが、江戸時代の作為された大量の系図群を見ると、それよりも同氏の一族は姓を「源平藤橘」に替え、姿を変えて生き延びていったとした方が良い。 宮氏の素性 たとえば、室町時代から戦国時代にかけて備後最大の勢力を誇った宮氏である。同氏の主流は戦国の荒波の中で毛利氏と対立し、敗れて滅んでいったが、今まで藤原摂関家の一人平安中期に活躍した関白小野宮実頼の後裔とばかり考えられていた。室町期の宮氏は皆「藤原」を称しており、戦国初頭の宮氏の画像の賛文に「小野宮四海の政に接し、聖化を翼賛す。居士以ってその苗裔たり」とあって、宮氏自身それを称していたことがわかる。 ところが、先年発刊された『東城町史』で驚くべき事実が明らかにされた。『庶軒日録』という室町時代の禅僧の日記に「奴可入道西寂は備後の宮の先祖なり…」と記されていたのだ。このことは近世の系図記録には一切記されていない。 奴可入道は、『平家物語』に出てくる河野氏によって討ち取られた奴可入道である。奴可は旧郡名(現比婆郡東半)だから、入道は古代以来の豪族の後裔であろう。入道西寂の活躍を室町時代の宮氏の人々が知らなかったはずはない。では、なぜ宮氏は入道が自分たちの先祖であると言わなかったのか。おそらくそれは『平家物語』に登場する入道の最後が余リカッコのいいものではなく、宮氏がそれを公言するのがはばかられるものだったからに違いない。 つまり、支配者となった武士は先祖をありのままに受け入れるのではなく、『選んだ』のである。こうして、本来の先祖は忘れられ、武士に『人気のある』源氏や平家、藤原氏が彼等の先祖になった。我々は、こうした捏造された系図や記録に惑わされることなく、現地に残る遺跡や同時代の史料に基づいて、郷土史を再構築しなければならない。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会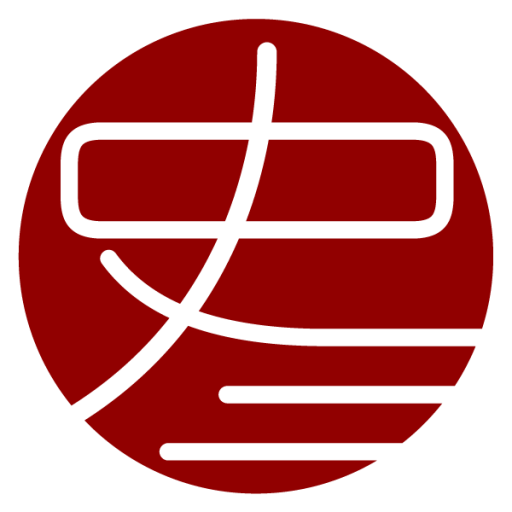
備陽史探訪の会古代史部会では「大人の博物館教室」と題して定期的に勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 大人の博物館教室
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 中世を読む




