神辺の原点村尾郷(捏造された神辺城の歴史)
「備陽史探訪:138号」より
小林 定市
1、はじめに
毛利元康の事跡を究明していたところ、神辺城の通説に多くの疑義が伏在していることが判明した。例えば福山・神辺では、天文十七・八年の神辺城合戦は常識とされてきた。しかし、これは福山と神辺だけの独善的な常識で、当時村尾城の城名は記録されていても一級史料に神辺城の記載は全く認められなかった。
①城を攻撃した大内義隆と奉行は、村尾城・村尾要害と記載し地名を神辺と記録している。
②大内義隆の下命で攻撃に加わった毛利・平賀軍は、村尾城と神辺の両地名を併記していた。
③神辺・福山では神辺城と書かれているが、当時の記録ではなく、何れも後年の編纂資料に依るものであった。
山口では大内時代の古文書が整理発刊され、村尾城攻撃の史料が年月日の順を追って記録されている。山口に比べ神辺・福山では、合戦の史料集さえ未だ編纂されず歴史の真相は曖味で総括されていない。
2、大内義隆の村尾城・要害
実は天文年間に神辺攻撃を下命したのは山口の大内義隆で、攻撃の先鋒は安藝の毛利軍や平賀軍であった。義隆は感状や書状に合戦場の地名を書いているが、神辺城と書かず村尾城又は村尾要害と記していた。何故義隆は神辺城と書かなかったのか、単純な疑問の答が神辺では何一つ見出せない。実は村尾城は実在していても、当時は神辺城と呼称されておらず城名が変化するのは後年の出来事である。
大内義隆が吉川元春に宛てて発給した、天文十七年(一五四八)十二月の感状に
六月十八日・廿日、村尾城下合戦の時に於いて、営手の輩の手負い注文を一見し候らい了ぬ
(『吉川家文書』五〇八)
と戦場の地名を村尾城下と記している。
また小早川隆景に宛てた天文十八年二月の感状にも
廿六日、村尾要害麓合戦の時に於いて、営手の衆の軍忠の注文次第を披見せじめ候
(『小早川家文書』二六七)
と、村尾要害麓合戦と記している。義隆は吉川・小早川の他にも、有地兼成や湯浅元宗に対し村尾城と書いた感状を発給している。驚いたことに山口に居た義隆の方が備後の地名を正確に把握していたのである。
義隆が備後に派遣した検使の杉甲斐守・小原隆言。弘中隆兼から、今回の攻撃目標地が村尾城・要害であるとの報告を受け、備後からの戦況報告書を披見した義隆が感状に村尾城・要害と記載していたのである。
そのため感状の字句を注意して読むと、義隆は戦場を「村尾城下合戦」「村尾要害麓合戦」と書いており、当時の城名は村尾城が正しく神辺城は未だ存在していなかった。
3、元就の神辺と平賀の村尾城
義隆の下命で村尾城を攻撃した毛利元就は、家臣の馬屋原詮費や福原貞俊に対し、合戦場の地名を神辺と記した証文を発給している。元就の書状からも判明するように、天文年中は合戦場が神辺で、城名は村尾城と呼称され神辺は村尾城下の小字にしか過ぎなかった。
元就と共に村尾城を攻撃した平賀隆宗は、
村尾城主山名理興は我が宿怨の敵であるから是非我が手兵を以て之を撃滅し、積年の墳怨を晴らす
と言って対塁を築いたが、天文十八年七月三日に俄に病没した。併し遺臣等は隆宗の遺志を奉じ一致協力して、日夜攻撃を続行して遂に九月四日落城させている。
備後の戦況を記録した電大内氏実録』義隆)にも、
平賀隆宗、天正十八年四月以来、我が一手を以て村尾城を囲みて神辺に在陣せしが、病に罹り七月三日死去せり。九月三日平賀兵村尾城を取る
と記している。
実は『大内氏実録』が一番正確に当時の状況を把握しており、村尾城の一郭に神辺が存在していたことが判明した。義隆は山名理興の逆襲を警戒して、村尾城の城督に重臣の青景隆著を任命している。
数ヵ年に亘る神辺合戦の結果、何時しか神辺の地名が有名となり、平賀。大内勢に占領された村尾城名は住民からも忌み嫌われ、年月の経過と共に忘れ去られたようである。
神辺の地名由来を明確にする史料に欠けるが、神辺の地名起因に関する有力な一説にとして、天別豊姫神社に寄附された山林や田畑の神社領を、土地の人が尊称して「神の辺(ほとり)の地」神辺と呼んだ、との説が始まりとも云われている。
『毛利元就卿伝』の筆者は、その一節の「備後山名氏の滅亡」の中に(附記)を別記し、
神辺城は村尾城ともいう、義隆の感状に村尾城とある。是より推断すれば、神辺は地名、村尾はその城名
と推定されており、著者の慧眼は村尾城と神辺の関係を正確に評価されていた。
4、杉原景盛の村尾郷記録
杉原盛重の次男景盛は死の四ヶ月前、備後から遠く放れた鳥取県西伯郡西伯町の馬場村の人幡宮を再興し、棟札叉は書面に村尾の地名由来を書き残していた。
『伯耆志』に依ると、
天正十二年(一五八四)甲申年仲呂(四月)上旬、備後國安那郡村尾郷、神辺城主杉原兵庫頭景盛
との記録を伝えている。景盛は神辺城が立地していた場所を村尾郷と書いており、村尾城の由来は地名の村尾郷から城名を村尾城と付けていた。
以上、大内義隆に依る天文十二年以降六ヶ年に亘る村尾城攻防戦で、合戦場の小字と推定できる固屋口・七日市・神辺の中で、特に激戦地の神辺が一躍有名となり、後年に至り村尾城から神辺城に城名が何時しか変化していたのである。
領主杉原氏の没落という悲劇が影響してか、重要な古文書や古記録が地元から湮滅し、村尾郷名の存在そのものまで地元住民から忘れ去られていたのである。景盛と義隆に依る村尾城の記述内容は一致し、馬場村と山口の記録から安那郡の失われていた郷名が判明した。
5、神辺表の長和八幡
天正十二年(一五八四)十月朔日頃と推定できる、小早川隆景宛真木嶋昭光の奉書に
御領所の儀に付き、両度申し入れ候と雖も、(中略)此の度輝元へ仰せ達せられ、神辺表に於いて一廉(相応な)御進上候様、御馳走御思し食し頼まれ候
(『小早川家文書』五四八)
と、本能寺の変の二年後帰京を諦めた足利義昭は、備後で生活出来る領所を輝元に所望し、交渉の早期解決を促進する目的から隆景に助力を要望していた。
文面の「神辺表」に付いて、足利義昭が要求した神辺表は文字通り神辺城下と推定された解説書も見られる。しかし、神辺表の表現は「国表・江戸表」と同義語の幅のある用語で、狭い意味での神辺城下を特定した表現ではなかった。領主不在となっていた「杉原景盛の旧支配領域」、即ち神辺城の支配権が及んでいた範囲を輝元は「神辺表」と書いていた。
早速隆景から輝元に斡旋を進めた結果、輝元から真木嶋昭光に返書があったらしく、天正十二年十一月十八日と推定できる三宮就辰宛真木嶋昭光の書状に、
御座所の儀、大守(輝元)江仰せ出だされ候処、早速御請けに及ばるるの段、御感悦此の御事に候、然れば急度御進上渡され候様御馳走御祝着たるべく候 (以下略)
『山口県文書館。毛利家文庫遠用物所収文書』
と真木嶋昭光は今後の領所交渉に明るい期待をかけていた。
翌年の正月廿九日頃、交渉は大詰めを迎えていたらしく毛利輝元は二宮就辰に宛てて、
長和の儀、是非とも二百貫の所ハ抜き候ハて進上候ハてハと、小林(家孝)回の事に候、(中略)定めて隆景・元春(吉川)は罷り出候条、叉彼の者を以て種々申さるべくと存じ候、申し張り候て三百貫抜き候らいても、公方様(足利義昭)への時儀(挨拶)も欠け候条、長和の儀進上すべき迄に候、夫領の儀いつもいつも仰せられ候条、三百貫の地進上候て、せめて右の所を差し置かれ候様申すべく哉と存じ候
(『廣島県史』古代中世資料編V譜録)
と、長和三百貫の地の要求も併せて受容れ交渉を妥結させる様命じている。
その結果実現したのが沼隈郡長和村(瀬戸町)周辺一帯を含めた、千三百五十石『毛利氏八箇國御時代分限帳』の領所であった。寛永十六年(一六三九)、長和村の福居八幡宮(『水野記』十三)は
社領五拾貫、山名氏に至って再興、其の後毛利家に及び天正年中義昭将軍叉再興す、(中略)本社(本殿)及び拝殿・艮大明神社今に到って残る也
と、足利義昭が福居八幡を再興したとする伝承を伝えていた。
最初に『水野記』を読んだ時の感想は、義昭の長和領有説を裏付ける史料に欠け半信半疑であった。しかし、輝元の異母兄弟に当る三宮就辰に宛てた「長和を進上」と書いた文言から史実と確定した。義昭が備後を去って五十一年後に書かれた、福居八幡の足利将軍の社殿造営説は歴史的事実を反映した文書であった。
6、児玉元信領の「神辺の内」
天正十四年十二月三日、児玉元信に宛てた毛利輝元の所領宛行状に、「神辺の内岩成・藪路・坂田」の地名が記載されていた。室町時代は神辺とは無縁であった地域の、岩成・藪路・坂田が「神辺の内」と書かれていたのである。
この文書を解説された某先生は、「神辺の内」に付いて「神辺は岩成。藪路・坂田辺り迄拡がっていた程広大な面積の地域」と、地名の精査も行わず自己の学説を述べられていた。しかし、宛行状を発給した輝元の本音は「神辺の面積」広域性を意図したものでなく、神辺城の支配領域を「神辺の内」と書いていたのである。
輝元は新たに杉原景盛跡の神辺城を直轄領に組込んだため、旧来の神辺城領を無難に表現する目的から「神辺の内」と書いたようである。そのため「神辺の内」には、「毛利家の備後支配領域」といった言外の意味を読取る事も必要である。
「神辺の内」を無批判に読むと、神辺城を中心とした神辺の呼称地域は、岩成や藪路に坂田までも含んでいたことになる。しかし、岩成とは深津郡石成庄を意味し地頭も判明している。藪路は深津郡吉津庄内の藪路村、坂田は深津郡杉原保内の坂田村であった事を裏付ける、室町戦国時代の史料が伝えられている。
神辺は天文十八年以降の合戦で有名となった新興激戦地名で、村尾から変って僅か三十余年程度経過して書かれた輝元の宛行状である。この神辺の歴史経過を念頭に入れて文書を読まないと、文字をいくら正確に読んでも正答を得る事は難しい。
7、天正十五年の神辺宿は沼隈郡
比較的新しい歴史の地名研究書である、平凡社の『広島県の地名』神辺の條に依ると、毛利時代から神辺宿が存在していたと書かれている。
その裏付け史料として、天正十四年(一五八六)十二月十九日、毛利輝元が二宮就辰に宛てた書状に、
関白様(豊臣秀吉)御下りならば神辺にて御宿調え候事
(『廣島県史』古代中世資料編・譜録)
の文書が証拠史料として提示されている。
時は戦国時代の終末期、天正十五年の数年前まで秀吉は毛利軍を相手に激烈な戦闘を展開していた。秀吉がいくら豪胆でも、敵対していた敵方の城下町に、無用心に出向いて宿陣するとは考え難いことである。
十四日後に輝元は訂正通達を二宮就辰に送っている。天正十五年正月三日の書状に依ると
中山・赤坂(沼隈郡)御宿入目(入費)の儀、注文を以て申し聞かせ候、其の上宿替えの奉行共に奉書を遣わし候
と、二度目の通達を出していた。場所は神辺城の西南方約二里半先の赤坂を指定していたのである。
島津氏征討のため、秀吉の軍勢が備後に宿陣したのは輝元書状の二ヶ月後であった。宿陣地は安那郡の神辺か、それとも沼隈郡の赤坂村なのか、宿陣の正解記録が秀吉の家臣に依って記録されていた。
秀吉の宿陣記録とは『楠長譜下向記』で、同書の天正十五年二月の項には
十一日、備中のなか山御留。十二日、備後赤坂御留。十三日、同三原
と赤坂村が正解であった。
また同じ内容の(『九州御動座記』内閣文庫所蔵本)にも
十一日、備中のなか山迄 八里。十二日、備後赤坂迄 八里。但し此の所へ公方様(足利義昭)御出で候らいて、御太刀折紙にて御程を仰せられ候、御酒上に互いに銘作の御腰物参らさせられ候、則ち公方様御座所も赤坂の近所(津之郷村)也、備後のとも(鞆)の浦へ三里これあり。十三日、同國三原迄 上ハ里舟付
と兩書は赤坂村と記録しており、輝元の宿営設置場所は神辺領内の赤坂村であった。
天正十五年七月十七日、薩摩の島津氏を降伏させ秀吉の後を追って東上していた細川藤孝(幽斎)は、『九州道の記』に
備後の津(津之郷)の公儀(足利義昭)御座所に参上
と記している。翌日は鞆迄足を伸ばし暮方に発句を所望される。
名残ある 月やともづな 港ぶね
8、天正三十年の神辺宿も沼隈郡
次に天正三十年四月八日、毛利輝元に宛てた豊臣秀吉の朱印状(『毛利家文書』八七四)にも、
振舞の儀も色々造作の外に候間、神辺の御泊りより御書き立てを以て仰せ出され候、其の外一切無用の由
と、秀吉は昨夜宿泊した神辺の宿より「歓待と饗応を簡略化する様」指示し、肥前名護屋の輝元の陣に送り届けていた。
天正十四年十二月の輝元の書状と共に、此の関白秀吉の朱印状も神辺宿を裏付ける有力な根拠史料とされている。常識的には誰もが太閤や輝元の文面を信じ、江戸時代の神辺宿の存在を疑問視し難い朱印状の文面であった。
秀吉が朝鮮の役に名護屋下向した際の、詳細な宿泊記録が『豊臣秀吉九州下向記』に記されていた。天正三十年四月の同書に依ると
七日、晴、岡山を御立ちあって備中の矢懸(矢掛)に御着陣。八日、早天に細雨、午前晴、備後の杉原(山手村)の三賓寺に御着陣、矢懸より一里半
と記録され、狭義の神辺ではなんく神辺領内の沼隈郡山手村に宿陣していた。
秀吉は二度も神辺に宿陣した記録を残して居ながら、実際には神辺より一里半と二里半も離れた山手村と赤坂村に宿営していた。このように神辺の宿と記録されていても、史料の中身を分析すると近世の神辺宿とは異なる場所であるが判明した。
9、毛利輝元の神辺
以上、輝元が出した数通の神辺関係の文書を分析吟味した結果、輝元の神辺の文意は、広義の大きな神辺城領「神辺城の支配領域内の安那郡。深津郡。沼隈郡の村約六・七十ヶ村程度を含む」を一括して神辺と記載していた事が判明した。
輝元の立場から神辺の呼称を考えた場合、新所領に編入した杉原景盛の神辺領の末端地名は繁雑であった事から、神辺城領は神辺奉行に一任して神辺と記載していた様である。
四百年以上も昔の「神辺」の呼称を現代の歴史家が読むのであるから、解釈が異なるのは当然である。しかし、輝元が書いた神辺は神辺城領を想定した大きな神辺であった。一方近代の郷土史家の先生方が想定された神辺は、文字通りの狭小な城下町神辺の麓村であった。
10、神辺の備後守護所説
私の手元にある『神辺城をめぐる武将』と題する本に、
神辺城の歴史は、建武二年(一三三五)朝山景連が備後守護所を黄葉山に置いた事に始まり、元和五年(一六一九)大和郡山城から転封して来た水野勝成の福山移城によって終えます。
との建武二年築城説が、神辺の歴史の根幹常識とされてきた。
この通説は、神辺の戦国時代の地名「天文十八年頃の村尾郷や村尾城名」と、「村尾城から神辺城に城名が変った」経緯を全く理解していない江戸後期の著者が、思考に依り生み出した捏造の創作歴史であった。
このように通説と古文書の世界は全く別物で、神辺城の城名が付けられるのは、建武二年より三百十数年以降の出来事であった。福山地方の歴史の欠点は、史料の鑑定を行わず粗悪な資料を採用し玉石混清の歴史を定着させた惑乱させてきた。
備後守護所の調査を進めると、備後安國寺造営の関係から細川頼春が鞆を拠点としていた事は確実で、長門探題と備後守護を兼帯した足利直冬も引続き鞆を守護所としている。
山陽道を重視していたのであろうか、足利尊氏方の守護高師泰(長門探題と備後守護を兼帯)と高師冬に岩松頼宥等は、石成庄の勝戸山城で足利直冬方と交戦している。
其の後の、今川・渋川・細川諸氏の守護所を明らかにする事が出来ないが、岩松頼宥の時代から約八十年経過した永享五年(一四三三)、山名持豊と山名満―の兄弟が家督を巡って国府城(府中市)で争っている。以上が現在迄の判明している守護所又は拠点であり、備後守護の中で神辺を拠点として活躍した守護は知られていない。
11、慶長検地と村尾郷名問題
関ヶ原の合戦に、元康軍は局地戦で勝利したのであるが、毛利本隊は二日後の大合戦に参戦せず東軍の勝利に貢献し惨敗した。そのため元康の家族と家臣は、備後を去り長州の厚狭(山陽町)へ移封となった。
新しく入部した福嶋正則は神辺城主に福嶋正澄を任命し、翌年検地を実施して、村尾郷の神辺城下を麓村と村名を付け村高二千八百十六石余の大きな村を誕生させた。
福嶋検地に依って、村尾郷は麓村に地名が変ったのである。一般の村では旧称の庄・保・郷名が引続き用いられる例が多いのであるが、村尾郷の場合は神辺城との関係からか、山麓の麓「神辺」が選ばれたらしく麓村と村名が付けられた。
神辺城は建武二年から存在する城名と喧伝されてきた。しかし、その記録は捏造に依るものであり、確実な史料により万人が納得できる歴史に改めたいものである。
天文期の神辺城合戦の誤史は、著名な先生方により全国に発信されている。例えば(「毛利元就のすべて』新入物往来社)や(『大内義隆』平凡社)の末尾に編年年表があり、天文十七・八年の下段に神辺城合戦と記載され、当時実在しなかった城名が堂々と掲載されている。
近年は古代史の謎とされてきた聖徳太子について、「聖人視されてきた聖徳太子像は実像でなく、捏造されている」との説が有力視されている。福山地方でも誤った歴史情報は速やかに修正して、精選された情報を堂々と発信したいものである。
終わりに、幼少時から母の里に行く際は神辺駅で下車し、神辺城を見上げながら三日市・七日市・古城山と、古戦場の折れ曲がった神辺街道をとぼとぼと歩いた記憶が思い出される。見通しの悪い街路に不思議な魅力を感じながら、歩き始めて早くも七十余年が経ってしまった。古い街道沿いの町並みを想起しながら、神辺の戦国史の一端を纏める事が出来たのも宿縁なのであろうか。
https://bingo-history.net/archives/11115https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/03-31.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/03-31-150x140.jpg中世史「備陽史探訪:138号」より 小林 定市 1、はじめに 毛利元康の事跡を究明していたところ、神辺城の通説に多くの疑義が伏在していることが判明した。例えば福山・神辺では、天文十七・八年の神辺城合戦は常識とされてきた。しかし、これは福山と神辺だけの独善的な常識で、当時村尾城の城名は記録されていても一級史料に神辺城の記載は全く認められなかった。 ①城を攻撃した大内義隆と奉行は、村尾城・村尾要害と記載し地名を神辺と記録している。 ②大内義隆の下命で攻撃に加わった毛利・平賀軍は、村尾城と神辺の両地名を併記していた。 ③神辺・福山では神辺城と書かれているが、当時の記録ではなく、何れも後年の編纂資料に依るものであった。 山口では大内時代の古文書が整理発刊され、村尾城攻撃の史料が年月日の順を追って記録されている。山口に比べ神辺・福山では、合戦の史料集さえ未だ編纂されず歴史の真相は曖味で総括されていない。 2、大内義隆の村尾城・要害 実は天文年間に神辺攻撃を下命したのは山口の大内義隆で、攻撃の先鋒は安藝の毛利軍や平賀軍であった。義隆は感状や書状に合戦場の地名を書いているが、神辺城と書かず村尾城又は村尾要害と記していた。何故義隆は神辺城と書かなかったのか、単純な疑問の答が神辺では何一つ見出せない。実は村尾城は実在していても、当時は神辺城と呼称されておらず城名が変化するのは後年の出来事である。 大内義隆が吉川元春に宛てて発給した、天文十七年(一五四八)十二月の感状に 六月十八日・廿日、村尾城下合戦の時に於いて、営手の輩の手負い注文を一見し候らい了ぬ (『吉川家文書』五〇八) と戦場の地名を村尾城下と記している。 また小早川隆景に宛てた天文十八年二月の感状にも 廿六日、村尾要害麓合戦の時に於いて、営手の衆の軍忠の注文次第を披見せじめ候 (『小早川家文書』二六七) と、村尾要害麓合戦と記している。義隆は吉川・小早川の他にも、有地兼成や湯浅元宗に対し村尾城と書いた感状を発給している。驚いたことに山口に居た義隆の方が備後の地名を正確に把握していたのである。 義隆が備後に派遣した検使の杉甲斐守・小原隆言。弘中隆兼から、今回の攻撃目標地が村尾城・要害であるとの報告を受け、備後からの戦況報告書を披見した義隆が感状に村尾城・要害と記載していたのである。 そのため感状の字句を注意して読むと、義隆は戦場を「村尾城下合戦」「村尾要害麓合戦」と書いており、当時の城名は村尾城が正しく神辺城は未だ存在していなかった。 3、元就の神辺と平賀の村尾城 義隆の下命で村尾城を攻撃した毛利元就は、家臣の馬屋原詮費や福原貞俊に対し、合戦場の地名を神辺と記した証文を発給している。元就の書状からも判明するように、天文年中は合戦場が神辺で、城名は村尾城と呼称され神辺は村尾城下の小字にしか過ぎなかった。 元就と共に村尾城を攻撃した平賀隆宗は、 村尾城主山名理興は我が宿怨の敵であるから是非我が手兵を以て之を撃滅し、積年の墳怨を晴らす と言って対塁を築いたが、天文十八年七月三日に俄に病没した。併し遺臣等は隆宗の遺志を奉じ一致協力して、日夜攻撃を続行して遂に九月四日落城させている。 備後の戦況を記録した電大内氏実録』義隆)にも、 平賀隆宗、天正十八年四月以来、我が一手を以て村尾城を囲みて神辺に在陣せしが、病に罹り七月三日死去せり。九月三日平賀兵村尾城を取る と記している。 実は『大内氏実録』が一番正確に当時の状況を把握しており、村尾城の一郭に神辺が存在していたことが判明した。義隆は山名理興の逆襲を警戒して、村尾城の城督に重臣の青景隆著を任命している。 数ヵ年に亘る神辺合戦の結果、何時しか神辺の地名が有名となり、平賀。大内勢に占領された村尾城名は住民からも忌み嫌われ、年月の経過と共に忘れ去られたようである。 神辺の地名由来を明確にする史料に欠けるが、神辺の地名起因に関する有力な一説にとして、天別豊姫神社に寄附された山林や田畑の神社領を、土地の人が尊称して「神の辺(ほとり)の地」神辺と呼んだ、との説が始まりとも云われている。 『毛利元就卿伝』の筆者は、その一節の「備後山名氏の滅亡」の中に(附記)を別記し、 神辺城は村尾城ともいう、義隆の感状に村尾城とある。是より推断すれば、神辺は地名、村尾はその城名 と推定されており、著者の慧眼は村尾城と神辺の関係を正確に評価されていた。 4、杉原景盛の村尾郷記録 杉原盛重の次男景盛は死の四ヶ月前、備後から遠く放れた鳥取県西伯郡西伯町の馬場村の人幡宮を再興し、棟札叉は書面に村尾の地名由来を書き残していた。 『伯耆志』に依ると、 天正十二年(一五八四)甲申年仲呂(四月)上旬、備後國安那郡村尾郷、神辺城主杉原兵庫頭景盛 との記録を伝えている。景盛は神辺城が立地していた場所を村尾郷と書いており、村尾城の由来は地名の村尾郷から城名を村尾城と付けていた。 以上、大内義隆に依る天文十二年以降六ヶ年に亘る村尾城攻防戦で、合戦場の小字と推定できる固屋口・七日市・神辺の中で、特に激戦地の神辺が一躍有名となり、後年に至り村尾城から神辺城に城名が何時しか変化していたのである。 領主杉原氏の没落という悲劇が影響してか、重要な古文書や古記録が地元から湮滅し、村尾郷名の存在そのものまで地元住民から忘れ去られていたのである。景盛と義隆に依る村尾城の記述内容は一致し、馬場村と山口の記録から安那郡の失われていた郷名が判明した。 5、神辺表の長和八幡 天正十二年(一五八四)十月朔日頃と推定できる、小早川隆景宛真木嶋昭光の奉書に 御領所の儀に付き、両度申し入れ候と雖も、(中略)此の度輝元へ仰せ達せられ、神辺表に於いて一廉(相応な)御進上候様、御馳走御思し食し頼まれ候 (『小早川家文書』五四八) と、本能寺の変の二年後帰京を諦めた足利義昭は、備後で生活出来る領所を輝元に所望し、交渉の早期解決を促進する目的から隆景に助力を要望していた。 文面の「神辺表」に付いて、足利義昭が要求した神辺表は文字通り神辺城下と推定された解説書も見られる。しかし、神辺表の表現は「国表・江戸表」と同義語の幅のある用語で、狭い意味での神辺城下を特定した表現ではなかった。領主不在となっていた「杉原景盛の旧支配領域」、即ち神辺城の支配権が及んでいた範囲を輝元は「神辺表」と書いていた。 早速隆景から輝元に斡旋を進めた結果、輝元から真木嶋昭光に返書があったらしく、天正十二年十一月十八日と推定できる三宮就辰宛真木嶋昭光の書状に、 御座所の儀、大守(輝元)江仰せ出だされ候処、早速御請けに及ばるるの段、御感悦此の御事に候、然れば急度御進上渡され候様御馳走御祝着たるべく候 (以下略) 『山口県文書館。毛利家文庫遠用物所収文書』 と真木嶋昭光は今後の領所交渉に明るい期待をかけていた。 翌年の正月廿九日頃、交渉は大詰めを迎えていたらしく毛利輝元は二宮就辰に宛てて、 長和の儀、是非とも二百貫の所ハ抜き候ハて進上候ハてハと、小林(家孝)回の事に候、(中略)定めて隆景・元春(吉川)は罷り出候条、叉彼の者を以て種々申さるべくと存じ候、申し張り候て三百貫抜き候らいても、公方様(足利義昭)への時儀(挨拶)も欠け候条、長和の儀進上すべき迄に候、夫領の儀いつもいつも仰せられ候条、三百貫の地進上候て、せめて右の所を差し置かれ候様申すべく哉と存じ候 (『廣島県史』古代中世資料編V譜録) と、長和三百貫の地の要求も併せて受容れ交渉を妥結させる様命じている。 その結果実現したのが沼隈郡長和村(瀬戸町)周辺一帯を含めた、千三百五十石『毛利氏八箇國御時代分限帳』の領所であった。寛永十六年(一六三九)、長和村の福居八幡宮(『水野記』十三)は 社領五拾貫、山名氏に至って再興、其の後毛利家に及び天正年中義昭将軍叉再興す、(中略)本社(本殿)及び拝殿・艮大明神社今に到って残る也 と、足利義昭が福居八幡を再興したとする伝承を伝えていた。 最初に『水野記』を読んだ時の感想は、義昭の長和領有説を裏付ける史料に欠け半信半疑であった。しかし、輝元の異母兄弟に当る三宮就辰に宛てた「長和を進上」と書いた文言から史実と確定した。義昭が備後を去って五十一年後に書かれた、福居八幡の足利将軍の社殿造営説は歴史的事実を反映した文書であった。 6、児玉元信領の「神辺の内」 天正十四年十二月三日、児玉元信に宛てた毛利輝元の所領宛行状に、「神辺の内岩成・藪路・坂田」の地名が記載されていた。室町時代は神辺とは無縁であった地域の、岩成・藪路・坂田が「神辺の内」と書かれていたのである。 この文書を解説された某先生は、「神辺の内」に付いて「神辺は岩成。藪路・坂田辺り迄拡がっていた程広大な面積の地域」と、地名の精査も行わず自己の学説を述べられていた。しかし、宛行状を発給した輝元の本音は「神辺の面積」広域性を意図したものでなく、神辺城の支配領域を「神辺の内」と書いていたのである。 輝元は新たに杉原景盛跡の神辺城を直轄領に組込んだため、旧来の神辺城領を無難に表現する目的から「神辺の内」と書いたようである。そのため「神辺の内」には、「毛利家の備後支配領域」といった言外の意味を読取る事も必要である。 「神辺の内」を無批判に読むと、神辺城を中心とした神辺の呼称地域は、岩成や藪路に坂田までも含んでいたことになる。しかし、岩成とは深津郡石成庄を意味し地頭も判明している。藪路は深津郡吉津庄内の藪路村、坂田は深津郡杉原保内の坂田村であった事を裏付ける、室町戦国時代の史料が伝えられている。 神辺は天文十八年以降の合戦で有名となった新興激戦地名で、村尾から変って僅か三十余年程度経過して書かれた輝元の宛行状である。この神辺の歴史経過を念頭に入れて文書を読まないと、文字をいくら正確に読んでも正答を得る事は難しい。 7、天正十五年の神辺宿は沼隈郡 比較的新しい歴史の地名研究書である、平凡社の『広島県の地名』神辺の條に依ると、毛利時代から神辺宿が存在していたと書かれている。 その裏付け史料として、天正十四年(一五八六)十二月十九日、毛利輝元が二宮就辰に宛てた書状に、 関白様(豊臣秀吉)御下りならば神辺にて御宿調え候事 (『廣島県史』古代中世資料編・譜録) の文書が証拠史料として提示されている。 時は戦国時代の終末期、天正十五年の数年前まで秀吉は毛利軍を相手に激烈な戦闘を展開していた。秀吉がいくら豪胆でも、敵対していた敵方の城下町に、無用心に出向いて宿陣するとは考え難いことである。 十四日後に輝元は訂正通達を二宮就辰に送っている。天正十五年正月三日の書状に依ると 中山・赤坂(沼隈郡)御宿入目(入費)の儀、注文を以て申し聞かせ候、其の上宿替えの奉行共に奉書を遣わし候 と、二度目の通達を出していた。場所は神辺城の西南方約二里半先の赤坂を指定していたのである。 島津氏征討のため、秀吉の軍勢が備後に宿陣したのは輝元書状の二ヶ月後であった。宿陣地は安那郡の神辺か、それとも沼隈郡の赤坂村なのか、宿陣の正解記録が秀吉の家臣に依って記録されていた。 秀吉の宿陣記録とは『楠長譜下向記』で、同書の天正十五年二月の項には 十一日、備中のなか山御留。十二日、備後赤坂御留。十三日、同三原 と赤坂村が正解であった。 また同じ内容の(『九州御動座記』内閣文庫所蔵本)にも 十一日、備中のなか山迄 八里。十二日、備後赤坂迄 八里。但し此の所へ公方様(足利義昭)御出で候らいて、御太刀折紙にて御程を仰せられ候、御酒上に互いに銘作の御腰物参らさせられ候、則ち公方様御座所も赤坂の近所(津之郷村)也、備後のとも(鞆)の浦へ三里これあり。十三日、同國三原迄 上ハ里舟付 と兩書は赤坂村と記録しており、輝元の宿営設置場所は神辺領内の赤坂村であった。 天正十五年七月十七日、薩摩の島津氏を降伏させ秀吉の後を追って東上していた細川藤孝(幽斎)は、『九州道の記』に 備後の津(津之郷)の公儀(足利義昭)御座所に参上 と記している。翌日は鞆迄足を伸ばし暮方に発句を所望される。 名残ある 月やともづな 港ぶね 8、天正三十年の神辺宿も沼隈郡 次に天正三十年四月八日、毛利輝元に宛てた豊臣秀吉の朱印状(『毛利家文書』八七四)にも、 振舞の儀も色々造作の外に候間、神辺の御泊りより御書き立てを以て仰せ出され候、其の外一切無用の由 と、秀吉は昨夜宿泊した神辺の宿より「歓待と饗応を簡略化する様」指示し、肥前名護屋の輝元の陣に送り届けていた。 天正十四年十二月の輝元の書状と共に、此の関白秀吉の朱印状も神辺宿を裏付ける有力な根拠史料とされている。常識的には誰もが太閤や輝元の文面を信じ、江戸時代の神辺宿の存在を疑問視し難い朱印状の文面であった。 秀吉が朝鮮の役に名護屋下向した際の、詳細な宿泊記録が『豊臣秀吉九州下向記』に記されていた。天正三十年四月の同書に依ると 七日、晴、岡山を御立ちあって備中の矢懸(矢掛)に御着陣。八日、早天に細雨、午前晴、備後の杉原(山手村)の三賓寺に御着陣、矢懸より一里半 と記録され、狭義の神辺ではなんく神辺領内の沼隈郡山手村に宿陣していた。 秀吉は二度も神辺に宿陣した記録を残して居ながら、実際には神辺より一里半と二里半も離れた山手村と赤坂村に宿営していた。このように神辺の宿と記録されていても、史料の中身を分析すると近世の神辺宿とは異なる場所であるが判明した。 9、毛利輝元の神辺 以上、輝元が出した数通の神辺関係の文書を分析吟味した結果、輝元の神辺の文意は、広義の大きな神辺城領「神辺城の支配領域内の安那郡。深津郡。沼隈郡の村約六・七十ヶ村程度を含む」を一括して神辺と記載していた事が判明した。 輝元の立場から神辺の呼称を考えた場合、新所領に編入した杉原景盛の神辺領の末端地名は繁雑であった事から、神辺城領は神辺奉行に一任して神辺と記載していた様である。 四百年以上も昔の「神辺」の呼称を現代の歴史家が読むのであるから、解釈が異なるのは当然である。しかし、輝元が書いた神辺は神辺城領を想定した大きな神辺であった。一方近代の郷土史家の先生方が想定された神辺は、文字通りの狭小な城下町神辺の麓村であった。 10、神辺の備後守護所説 私の手元にある『神辺城をめぐる武将』と題する本に、 神辺城の歴史は、建武二年(一三三五)朝山景連が備後守護所を黄葉山に置いた事に始まり、元和五年(一六一九)大和郡山城から転封して来た水野勝成の福山移城によって終えます。 との建武二年築城説が、神辺の歴史の根幹常識とされてきた。 この通説は、神辺の戦国時代の地名「天文十八年頃の村尾郷や村尾城名」と、「村尾城から神辺城に城名が変った」経緯を全く理解していない江戸後期の著者が、思考に依り生み出した捏造の創作歴史であった。 このように通説と古文書の世界は全く別物で、神辺城の城名が付けられるのは、建武二年より三百十数年以降の出来事であった。福山地方の歴史の欠点は、史料の鑑定を行わず粗悪な資料を採用し玉石混清の歴史を定着させた惑乱させてきた。 備後守護所の調査を進めると、備後安國寺造営の関係から細川頼春が鞆を拠点としていた事は確実で、長門探題と備後守護を兼帯した足利直冬も引続き鞆を守護所としている。 山陽道を重視していたのであろうか、足利尊氏方の守護高師泰(長門探題と備後守護を兼帯)と高師冬に岩松頼宥等は、石成庄の勝戸山城で足利直冬方と交戦している。 其の後の、今川・渋川・細川諸氏の守護所を明らかにする事が出来ないが、岩松頼宥の時代から約八十年経過した永享五年(一四三三)、山名持豊と山名満―の兄弟が家督を巡って国府城(府中市)で争っている。以上が現在迄の判明している守護所又は拠点であり、備後守護の中で神辺を拠点として活躍した守護は知られていない。 11、慶長検地と村尾郷名問題 関ヶ原の合戦に、元康軍は局地戦で勝利したのであるが、毛利本隊は二日後の大合戦に参戦せず東軍の勝利に貢献し惨敗した。そのため元康の家族と家臣は、備後を去り長州の厚狭(山陽町)へ移封となった。 新しく入部した福嶋正則は神辺城主に福嶋正澄を任命し、翌年検地を実施して、村尾郷の神辺城下を麓村と村名を付け村高二千八百十六石余の大きな村を誕生させた。 福嶋検地に依って、村尾郷は麓村に地名が変ったのである。一般の村では旧称の庄・保・郷名が引続き用いられる例が多いのであるが、村尾郷の場合は神辺城との関係からか、山麓の麓「神辺」が選ばれたらしく麓村と村名が付けられた。 神辺城は建武二年から存在する城名と喧伝されてきた。しかし、その記録は捏造に依るものであり、確実な史料により万人が納得できる歴史に改めたいものである。 天文期の神辺城合戦の誤史は、著名な先生方により全国に発信されている。例えば(「毛利元就のすべて』新入物往来社)や(『大内義隆』平凡社)の末尾に編年年表があり、天文十七・八年の下段に神辺城合戦と記載され、当時実在しなかった城名が堂々と掲載されている。 近年は古代史の謎とされてきた聖徳太子について、「聖人視されてきた聖徳太子像は実像でなく、捏造されている」との説が有力視されている。福山地方でも誤った歴史情報は速やかに修正して、精選された情報を堂々と発信したいものである。 終わりに、幼少時から母の里に行く際は神辺駅で下車し、神辺城を見上げながら三日市・七日市・古城山と、古戦場の折れ曲がった神辺街道をとぼとぼと歩いた記憶が思い出される。見通しの悪い街路に不思議な魅力を感じながら、歩き始めて早くも七十余年が経ってしまった。古い街道沿いの町並みを想起しながら、神辺の戦国史の一端を纏める事が出来たのも宿縁なのであろうか。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会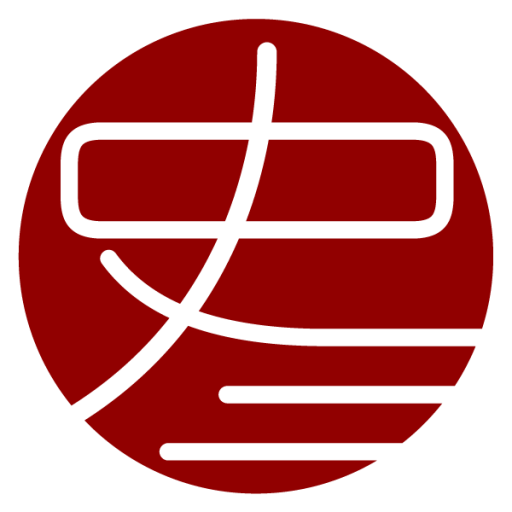
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 中世を読む




