京都の大覚寺文書と末寺明王院(捏造された寺伝について)
「備陽史探訪:150号」より
小林 定市
目次
一、水野領真言宗大覚寺五末寺
京都嵯峨の真言宗大覚寺と、福山藩領内の真言宗寺院が末寺となった経緯を記した文献が存在していた。その文献とは昭和五十五年九月に発刊された『大覚寺文書』で、同書の末寺帳の部に福山領内の五ヶ寺院名が記載されている。時代は水野勝成が領主であった寛永十五年(一六三八)が三ヶ寺、明暦二年(一六五六)と寛文十三年(一六七三)が各一ヶ寺で、特に明王院に注目したい。
備中 小田郡笠岡庄
●遍照寺 笠岡光明山(寺領三〇石)寛永十五年十月十六日被召加、(寛永年中の住僧宥仙)
●山王院 後月郡高屋村大乗山高山寺大坊、明暦二年(一六五六)八月晦日 被召加當住空範、
備後
●明王院 深津郡中道山園光寺、寛永十五年四月日被召加、(住僧宥将・寺領三十五石)
●福禅寺 沼隈郡鞆 海吟山、寛永十五年月日被召加、寛文十三年二月十三日代替御禮費意、(住僧榮観)
●廣山寺 安那郡仲條村玄洞山光明院、寛文十三年二月被召加、営住舜祐、證人鞆福禅寺、
明王院は草戸千軒の研究対象寺院として知られ、国宝の堂塔が現存することから全国的にも著名な寺院である。しかし、その反面同寺は謎の多い不透明な寺史を抱えており、大覚寺の末寺となった時期は何故か現在まで未公表とされてきた。
寛永十五年当時の明王院は深津郡内にあり、大覚寺文書には村名が記載されていない。村名が未記入であるため正確な場所は不詳であるが、本庄村の青木ヶ端にあったことは翌年の本堂棟札からも確実である。
末寺となった年の寛永十五年二月、水野勝成は島原の乱に参陣して活躍。同年三月には早くも帰国しており、明王院が大覚寺と本末関係を結んだ寛永十五年四月には、備後領内に居て政務に取組んでいた筈である。
明王院は大覚寺と本末契約を結んだことが契機となり、急ぎ領内の真言宗筆頭寺院に相応しい寺観の整備に着手した。勝成は本庄村から城下町(旧野上村)南方の奈良屋町(干拓地)に移転させ、早速本堂の新築に着手したらしく、翌寛永十六年六月「大檀那当所領主水野日向守 住持宥将上人」と記した本堂棟札を伝えている。
文書の記載順は備中から始まり遍照寺・山王院(高山寺)に続き、備後の明王院・福禅寺・廣山寺の五ヶ寺が末寺として記載されている。前記の五ヶ寺は何れも福山城主水野勝成の所領内の寺院であった。
寛永十六年三月、勝成は領内の寺社に対し旧記を提出させた。その時遍照寺の住僧宥仙は「備中國真言宗隋一の寺也、古来より末寺十二ヶ寺あり」との寺伝を提出している。
その後幕府転覆計画が判明した承応事件に、三代水野勝貞の家臣石橋が連座していたことが判明。そこで勝貞は幕府に恭順の意を表す必要性から、徳川家を祀る大寺社の建設計画を樹てた。ところが当時の水野家は財政が逼迫していたことから新造計画は中止となった。そこで建設計画を自紙に戻し明王院を草戸の常福寺と合併させ、寺観の一新を図り庫裏と書院を移築し書院に徳川家光を祀り盛大な法要を行った。
笠岡遍照寺の宥仙が、何時頃から明王院の住職となったのか定かでない。しかし、合併が確認できる明暦二年(一六五六)の頃には新明王院の筆頭住僧となっていた。宥仙は水野勝貞お気に入りの僧として高く評価され、前住の遍照寺に寺領三十石が与えられ特別優遇されていた。
二、福山城築城と明王院
元和五年(一五一九)八月、水野勝成は備後南部十万石の領主として入部した。早速福山城の築城に着手するのであるが幕府の援助もあり、元和八年八月廿八日には天守閣の上棟式を行っている。
福山築城の地鎮祭を行った僧は、本庄村の青木ヶ端にあった明王院の住僧宥将と伝えられている。宥将と勝成は、入部当初から特別親しい関係にあった。
勝成と不可分の関係にあった明王院は、前述の経緯から大覚寺派筆頭の中本山の寺に昇格し、末寺は四十八ヶ寺あったと伝えられている。奈良屋町の新本堂の行方であるが、草戸の常福寺と合併した際に移築され書院に使用されたと伝えている。
応仁の乱以降大覚寺は荒廃していたらしく、大覚寺再建の動きは後陽成・後水尾天皇の加護を得て、三十六世空性法親王(後陽成院の実弟)の時代から始まり、三十七世尊性入道親王(後陽成院の第五皇子)の門主時代にほぼ成し遂げられた。
一見勝成と空性法親王や尊性入道親王の接点は無さそうに見える。しかし、勝成を備南十万石の大名に引立てた恩人は徳川秀忠で、秀忠の娘和子(東福門院)は後水尾天皇の皇后となり入内している。尊性入道親王は後水尾天皇の実弟であった事から、大覚寺の再建に福山領内の真言宗寺院の増加を図った支援策は、東福門院と徳川幕府への間接的な恩返しとなり、勝成の感謝の念が真言宗寺院を纏めて大覚寺派とした。
寛永十五年八月、空性法親王は四国遍路に旅立っている。伊予の龍光院・地蔵院・石手寺の順に末寺に加え、帰途は安藝の厳島の大願寺にまで足を伸ばし、更に鞆の福禅寺と笠岡の遍照寺も末寺とするなど成果を挙げた四国遍路であった。
三、大覚寺と明王院の寺歴
改めて本末契約を交わした寛永十五年の僧を比較してみると、大覚寺は三十七世尊性入道親王の時代で、明王院の方は十七世宥将の時代であった。世代数は宥将より尊性入道親王の方が二十世も多く、大覚寺が三十世も多いことは明王院の方が遥か後世に創建された寺である事を意味している。大覚寺は嵯峨天皇の離宮で、空海が入滅してから四十四年経過した、貞観十八年(八七六)に開基された門跡寺院であった。
明王院の住職の世代数を手掛かりとして、開基年を逆算割出しする方法がある。江戸時代中期以降の明王院住職の十世の総年数を加算し、十世で割ると一世代「十九年半」の平均年数が出る。
仮に水野勝成が備後に入部した元和五年を基準年として、宥将以前の十六世の住僧に十九年半を掛算して出た答え(三百十二年昔)の年、即ち徳治二年(一三〇七)頃前後が大体の開基年の目安となる。
大正時代の明王院住職龍池(和田・片山)密雄(一八四三~一九三四)師は、安那郡道上村の出身で高野山と大覚寺六十世管長をも兼務されていた。当然大覚寺の前記文書を確認された筈である。しかし、肝心な末寺記録は何故か明王院からは今以て公表されていない。
四、明王院の梵鐘と寺伝問題
合併当時の明王院には梵鐘が無かった。宥仙は住持に就任すると梵鐘鋳造を急がせ、翌明暦三年(一六五七)十一月に完成させた。新鋳した梵鐘の池の間に、宥仙は鏨で「沼隈郡草戸之精舎中道山園光寺明王院門説大同二年平城皇帝之嘉運吾祖野山大師之開基也」と陰刻させ、開基を野山大師としていた。
この陰刻が本庄村の明王院を指すものか、それとも常福寺を意味するものか定かでない。合併した寺院の開基である以上、明王院と常福寺の二ヶ寺を記載するのが常道である。何故宥仙は二ヶ寺の開基を記さなかったのか大きな謎である。
鐘は本堂のご本尊に向かって撞くのが正式とされ、そのため鐘楼は本堂に向けて建てられている。宥仙により開基に新任された「天下りの野山大師」から送られてきた梵鐘の音に、本尊の十一面観音菩薩(平安時代後期作。余所からの移動仏像)は大変驚かれた事であろう。膨大な財力を投入して開基した地頭の長井頼秀は、知らぬ間に「野山大師」と不法登記され大憤慨した事であろう。
梵鐘は太平洋戦争にも供出されなかったらしく、三百五十余年前の鋳造当時の侭の形を今に伝えている。そのため梵鐘の南側に立てば、誰でも陰刻銘文を読むことが出来る。此の銘文が史書に記載されなかった理由は、僧侶や史家は梵鐘の年月日を読んでも銘文を省略したらしい。
宥仙の後住十九世宥翁は、梵鐘鋳造から三十三年後の元禄三年(一六九〇)に本堂の修復を行なうと、新寺伝を創作し「中道山明王密院者相伝曰、大同之年我弘法大師創基」と棟札に記し、先師の教えに背き知名度で勝負と「横滑り弘法大師」に登記替えを行った。史家と宥翁以降の現住・檀家や信者は、梵鐘の銘文を読まずに鐘を撞いていたのであろう。
その他の寺伝として、俳諧師の野々口立圃は『草戸記』に、
件の王塔(五重塔)は画工金岡(巨勢)か母此所に居住せしか、末代のじるし、又は後世菩提のために建立して
と巨勢金岡の建立説を書いている。このように江戸時代になると、三人の三様の「鳶の油揚げ」作戦を展開し妄説作りに狂奔していた。
歴史学に於いては古資料優先の原則がある。『草戸記』と梵鐘と棟札の作成年代を比較すると明らかに棟札が一番遅い。福山では資料採用の原則は無視され、明王院では一番遅く捏造された寺伝の資料価値が高いとして無批判に妄信されてきた。
明王院は寺の権威付けには手段を選ばず、偽文書を作成した凄腕の怪僧がいた。水野勝成との早くからの関係を強調するためか、「元和七年の常福寺本堂再興棟札」二本と「寛永十四年の水野勝成下知状」まで巧妙に偽造し、高名な史家も史料鑑定を誤る程の出来映えであった。
五、奈良西大寺と常福寺の関係
明王院は水野勝貞の強行合併が影響したのか、常福寺時代の建物以外は中世史料を何も伝えていない。合併で常福寺は根無し草となり捏造寺伝が史実の如く公認されてきた。
常福寺の本山が奈良の真言律宗西大寺であったことは周知の事実である。明徳二年(一三九一)の『西大寺坊諸国末寺帳』と、文亀二年(一五〇三)五月の『西大寺諸国末寺帳』惣合三百十八ヶ寺の中に、草出常福寺の記載が確認できる。
西大寺と常福寺の本末関係が途絶えた年は不明で、確実な史料は残念ながら見当たらない。しかし、参考となる史料に寛永十年(一六三三)三月の『西大寺諸国末寺帳』がある。同帳には尾道の浄土寺は記載されていても常福寺は消えている。
前記の文亀と寛永の二史料を総合的に判断すると、室町戦国時代草戸千軒を繁栄に導いたのは、草戸の領主(地頭)であった備後守護山名一族と、その代官渡辺一族に越中守兼が活躍した時期である。両支配者が草戸を放棄した十六世紀の半ば頃、草戸は衰微し経済的な行き詰まりから離脱に至ったようである。
草戸の支配権について出典は明らかにされていないが、草戸と草戸千軒は無主の地であるとする誤説が近代に至って蔓延した。地頭は長井氏に続き山名氏が活躍していたことは明白な史実である。しかし、温和な福山市民は誰も異議を唱えない。
また地頭が新開開発に関与した事例も報告されている。南北朝時代安藝沼田庄の地頭小早川氏が、「沼田川の新開開発を推進していた」事例が確認されており、長井氏も草戸地先の草戸千軒を開発し繁栄策を計画し実行に移したことであろう。
長井氏は承久の乱の後に長和庄の地頭に補任された。幕府が蒙古来襲に備え防禦を進めた文永十年(一二七三)の頃、領家悲田院と下地中分を行っている。当時備後の御家人には長門防衛の軍役が下命されており、国難の非常事態に対応する海上拠点となる東側(草戸)が必要となり、悲田院に下地中分を申し込むと快く了承されたようである。
九州・長門防衛は期間不明の先が見えない軍役であり、長和庄内の港湾可能地の要求は単に長和長井氏の単一要望でなく、関東評定衆家・備後守護家・庶家一族を含む田総長井一族の要求であったと考えたい。
和与に相前後して地頭の支配地区は更に分割され、南側(田尻村と水呑村の南半分)を田総長井氏が、北側(水呑村の北半分に草戸村。神嶋村・佐波村)を福原長井氏が支配したが後に安藝の福原に移った。
元応三年(元亨元年・一三二一)常福寺の観音堂に名前を残す、地頭の長井沙門頼秀は何故此の年に建立を進めていたのであろうか。建立以前から西大寺と深い関係にあったと想定できる史料が残されていた。元亨二年は興正菩薩叡尊上人の三十三回忌の年にあたり、弟子たちは盛大な遠忌供養を計画していた。
本山の報恩供養計画を知った頼秀も、翌年の元亨二年に観音堂を完成させるべく建設途中の努力をしていた。元応三年の墨書銘は建設中に繁栄を祈って書かれたもので、落成式は本山と同様翌年に施行され盛大な大法要も営んだことであろう。
天平宝字八年(七六四)、創建時の西大寺の金堂には弥勒菩薩が祀られていた。後世の諸書は西大寺が弥勒浄土相を写した兜率天宮と称されたと伝えている。ところが徳治二年(一三〇七)二月、火災があり弥勒像が焼失してしまった。弟子達は叡尊の弥勒信仰を継承発展させるため、三十三回忌を機に弥勒菩薩像の造立に踏み切った。新造の仏像は木造漆箔の像高三百八十六cmの弥勒菩薩坐像であった。
西大寺の弥勒菩薩造立は常福寺にも当然伝えられ、頼秀は次に建立する五重塔の本尊を弥勒菩薩と定め像造し勧請した。五重塔の本尊は小型木造の像高五十二・五cmの弥勒菩薩坐像(南北朝時代作)であった。
頼秀は像造だけでなく五重塔の伏鉢にも
右夫れ普く、兜率上詣の願望を遂げ、龍花下生の来縁を結ばせじめんが為
と、陰刻銘文を彫らせ深く弥勒を崇敬していた。西大寺では
叡尊は慈尊(弥勒)説法の制に詣でてその法を聴くところに逝かれた
『叡尊上人遷化之記』
と叡尊は弥勒に深く傾倒していた。五重塔の建立は叡尊への敬慕と関連しており、叡尊への憧憬が弥勒菩薩信仰にまで昇華されていた。
江戸時代に入ると弥勒菩薩は寺僧に依り歪曲され、胎蔵界の大日如来であると伝えられてきた。五重塔の本尊弥勒菩薩は建立時より現在まで不変であるが、仏名は弥勒菩薩から大日如来に変更された。
現在五重塔の正面に立つと、寺の由来と本尊を説明した平成十一年の案内説明板がある。説明板には「本尊 木造大日如来坐像」と書かれている。別の立看板にも右から「不動明王・大日如来・愛染明王」と三尊仏が標記されている。
近年の調査でも誤伝を見抜けず、「弥勒菩薩を大日如来」とする本尊間違いの本が発刊された。国宝に指定されている本尊の誤鑑定は、日本国中に二つとは無く福山だけであろう。何れにしても県市の大失態であると同時に福山市民の恥でもある。
六、明王院の大岩盤
現在明王院の東方の前庭に立ち、堂塔を眺めると落着いた作まいの寺院建築風景を見ることが出来る。ところが八百年昔の鎌倉時代末頃となると、未開発の衝撃的な景観が残されていたことが判明した。そこには御影石の凹凸に隆起した大岩盤が連なり原生林を形成していた。
現在は土中に隠れて見えないが、五重塔と観音堂の下の大部分は岩盤を平滑に削除した上に建立されていた。その痕跡は五重塔の背後の尾根に残されており、高さ約六mもある岩盤は深く傾斜に切下げられ、盛土の上に堂塔が建設されている。
岩盤の範囲は不詳であるが、仮に五重塔の南縁側から観音堂の向拝の石段辺りまであったと仮定すると、南北の距離は二十六mとなる。また、西の尾根の下から東方に伸びた岩盤先は明らかでないが、岩盤に掘られた柱穴の位置を配慮すると約二十m程度あったと想定できる。
寺院の創建は堂塔の建立が最初と考えられるが、常福寺の場合は大岩盤の平滑化から始まった。日本には岩盤を開鑿する技術は平安初期にはなく、石加工技術が備後地方に伝えられたのは鎌倉時代末で、そこには教線の拡大を図り社会事業にも尽力した、叡尊の高弟と石工集団が岩盤開盤に従事し活躍していた。
沙門頼秀は観音堂の建立に先立ち、尾根筋と隆起している大岩盤約五百平方メートルを平滑化する大工事が可能か、前以て見極め岩盤開削工事の見通しと併行して建立に着手したのであろう。
七、西大寺と善養寺に常福寺
徳治二年(一三〇七)七月末から十数日、備中成羽川上流の航路を通すため、「笠神龍頭上下の瀬十余ヶ所」を開整する大工事が行われた。大事業を推進したのは、西大寺の末寺成羽善養寺の沙門尊海が大勧進となり、西大寺叡尊の高弟実尊が奉行となって行なわれた。石切工事は宋人石工伊行末の流れを汲む伊行経であった。此の石切技術を伝聞した頼秀は、常福寺の岩盤開鑿を実尊に要請したことであろう。
西大寺に成羽善養寺と常福寺が兄弟寺院の如く、大変深い関係あったことを記した古記録がある。永享八年(一四六三)の『西大寺坊 寄宿末寺帳』に依ると、当時西大寺内には宿坊十三ヶ坊があり、宿坊「東室一分」の十一番に善養寺、十二番に常福寺が記載されていた。
前記の寄宿末寺帳により常福寺は尾道の浄土寺(宿坊「二聖院分」)より、西大寺実尊や善養寺の方がより緊密な関係にあった事が判明した。大胆な推定を行うと実尊の後身が「東室一分」の宿坊となり西大寺内に残されていたのである。
裏付け史料は残されていないが、沙門頼秀は実尊に寺院開基と港湾開発に岩盤開鑿の技術援助を依頼し、援助の確約を得て観音堂の建立に着手したのであろう。実尊も草戸の優れた経済の拠点性に着日し、石工伊行経等を派遣して困難な開鑿工事に当らせたことはほぼ確実である。
西大寺は成羽川の工事に続き常福寺の大工事を行ったことから、宿坊帳面に善養寺の次に常福寺を記載したのであろう。寺伝として大同二年説を強調しても、岩盤平滑工事を鎌倉時代末以前に遡らすことは無理で主張は矛盾する。常福寺と成羽の工事内容を比較すると、常福寺の工事は成羽の工事と優るとも劣らない程の難事業であったと想定できる。
膨大な建設費用を要した常福寺の創建には、最初の頃は頼秀が一族の代表として建立を進めていたらしいが、幕府転覆とか武家社会の情勢が大きく変化した後は、頼秀が独力で五重塔や阿弥陀堂の建立に踏み切った可能性がある。
常福寺は強固な岩盤の上に建立されていたから、地震にも耐え七百年近くの長寿命を保つことが出来たのである。改めて頼秀の先見性に感心すると同時に、捏造史を生んだ近世史の背景の徹底的検討と、近世資料採用基準の見直しを課題としたい。
観音堂の基礎の下にある岩盤に柱穴跡があったことから、柱穴跡は再建された建物の痕跡であるとの説が主張されてきた。しかし、柱穴は足場用の柱穴として建立中の事故防止と安全対策のため掘られたものであった。足場用の証拠として、観音堂の縁側石の外側に東西各々二箇の柱穴が掘られており、距離は約十六mあるが中間に柱穴はない。
観音堂の前身小庵跡と想定された柱穴跡の図面を見ると、東西八・八mある梁には中間の支え柱穴跡が一箇もなく、西北角に必要な隅柱穴跡もなく建物の内の総柱も見当たらない。図面の通りに柱を立てると使用出来ない奇妙な建物となる。
柱穴跡を根拠として再建説の論文を書かれた人は、『国宝明王院本堂修理工事報告書』の「七十九頁の第百七図の三」の図面を模写されると、建造物の柱穴跡でないことに気付かれる筈である。再建説を書く前に原史料の分析検討を十分に行えば、誤説の「観音堂再建」説が一人歩きをする事態は避けられたであろう。
足場用の柱穴跡は観音堂下にだけ掘られていたのではなく、五重塔の周辺にも掘られていた。塔の西後方の傾斜した岩盤上には、幅九・六mの間に直径十三m以上の円形の柱穴跡が九ヶ所もある。九箇の柱穴が四方に掘られていたと仮定すると、足場用の柱穴は三十六箇必要となる。
八、国宝を建立した沙門頼秀
五重塔の建立者が明らかにされたのは、昭和十一年に郷土史家の浜本鶴賓が、(『備後史談』第十二巻十一号・明王院と草戸中洲の変遷に、五重塔の露盤銘文の研究)に沙門頼秀の名前を掲載したのが嚆矢である。爾来七十三年の長年月が経過するが研究は一歩も前進していない。
「百年河清を待つ」とは、黄河の濁流が澄むことを望んだ言葉とか。国宝の銘文が公開されて、早くも百年の四分の三もの歳月だけが無為に近付いて来る。現在の進め方では百年先でも心許なく心配である。
近世初頭まで常福寺の上空は綺麗に澄んでいた。強行合併に依る新明王院が誕生した時から、寺の上空を妖雲が漂い始め爾来三百五十余年一向に立ち去る気配は無い。妖雲を吹き飛ばすには大台風の襲来を祈願する以外に手段は無いのであろうか。
福山市で国宝の堂塔を建立した人物は、現在長井沙門頼秀が只一人である。頼秀は福山一番の文化功労者であるが、謂れの無い陰険な策謀により封印・冷遇されてきた。
地頭長井頼秀を歴史上の人物として登場させると、従来史家が「草戸は悲田院が支配していた」と、主張してきた学説が根幹から崩壊する事態となる。現在迄の学説を擁護し破綻を避けるため頼秀の業績に覆いをかけ、存在しない観音堂の再建説を強調してきた節がある。
郷土史は史家の面目を保つために存在するのではなく、郷土の発展に貢献した人物の顕彰を行うことも重要な仕事であろう。頼秀の偏見が一日も早く晴れ、明王院に頼秀の大銅像が建立される日を期待したい。
https://bingo-history.net/archives/12320https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/02/a5ab0dd3881a4da09f894b329301f72d.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2016/02/a5ab0dd3881a4da09f894b329301f72d-150x100.jpg中世史「備陽史探訪:150号」より 小林 定市 一、水野領真言宗大覚寺五末寺 京都嵯峨の真言宗大覚寺と、福山藩領内の真言宗寺院が末寺となった経緯を記した文献が存在していた。その文献とは昭和五十五年九月に発刊された『大覚寺文書』で、同書の末寺帳の部に福山領内の五ヶ寺院名が記載されている。時代は水野勝成が領主であった寛永十五年(一六三八)が三ヶ寺、明暦二年(一六五六)と寛文十三年(一六七三)が各一ヶ寺で、特に明王院に注目したい。 備中 小田郡笠岡庄 ●遍照寺 笠岡光明山(寺領三〇石)寛永十五年十月十六日被召加、(寛永年中の住僧宥仙) ●山王院 後月郡高屋村大乗山高山寺大坊、明暦二年(一六五六)八月晦日 被召加當住空範、 備後 ●明王院 深津郡中道山園光寺、寛永十五年四月日被召加、(住僧宥将・寺領三十五石) ●福禅寺 沼隈郡鞆 海吟山、寛永十五年月日被召加、寛文十三年二月十三日代替御禮費意、(住僧榮観) ●廣山寺 安那郡仲條村玄洞山光明院、寛文十三年二月被召加、営住舜祐、證人鞆福禅寺、 明王院は草戸千軒の研究対象寺院として知られ、国宝の堂塔が現存することから全国的にも著名な寺院である。しかし、その反面同寺は謎の多い不透明な寺史を抱えており、大覚寺の末寺となった時期は何故か現在まで未公表とされてきた。 寛永十五年当時の明王院は深津郡内にあり、大覚寺文書には村名が記載されていない。村名が未記入であるため正確な場所は不詳であるが、本庄村の青木ヶ端にあったことは翌年の本堂棟札からも確実である。 末寺となった年の寛永十五年二月、水野勝成は島原の乱に参陣して活躍。同年三月には早くも帰国しており、明王院が大覚寺と本末関係を結んだ寛永十五年四月には、備後領内に居て政務に取組んでいた筈である。 明王院は大覚寺と本末契約を結んだことが契機となり、急ぎ領内の真言宗筆頭寺院に相応しい寺観の整備に着手した。勝成は本庄村から城下町(旧野上村)南方の奈良屋町(干拓地)に移転させ、早速本堂の新築に着手したらしく、翌寛永十六年六月「大檀那当所領主水野日向守 住持宥将上人」と記した本堂棟札を伝えている。 文書の記載順は備中から始まり遍照寺・山王院(高山寺)に続き、備後の明王院・福禅寺・廣山寺の五ヶ寺が末寺として記載されている。前記の五ヶ寺は何れも福山城主水野勝成の所領内の寺院であった。 寛永十六年三月、勝成は領内の寺社に対し旧記を提出させた。その時遍照寺の住僧宥仙は「備中國真言宗隋一の寺也、古来より末寺十二ヶ寺あり」との寺伝を提出している。 その後幕府転覆計画が判明した承応事件に、三代水野勝貞の家臣石橋が連座していたことが判明。そこで勝貞は幕府に恭順の意を表す必要性から、徳川家を祀る大寺社の建設計画を樹てた。ところが当時の水野家は財政が逼迫していたことから新造計画は中止となった。そこで建設計画を自紙に戻し明王院を草戸の常福寺と合併させ、寺観の一新を図り庫裏と書院を移築し書院に徳川家光を祀り盛大な法要を行った。 笠岡遍照寺の宥仙が、何時頃から明王院の住職となったのか定かでない。しかし、合併が確認できる明暦二年(一六五六)の頃には新明王院の筆頭住僧となっていた。宥仙は水野勝貞お気に入りの僧として高く評価され、前住の遍照寺に寺領三十石が与えられ特別優遇されていた。 二、福山城築城と明王院 元和五年(一五一九)八月、水野勝成は備後南部十万石の領主として入部した。早速福山城の築城に着手するのであるが幕府の援助もあり、元和八年八月廿八日には天守閣の上棟式を行っている。 福山築城の地鎮祭を行った僧は、本庄村の青木ヶ端にあった明王院の住僧宥将と伝えられている。宥将と勝成は、入部当初から特別親しい関係にあった。 勝成と不可分の関係にあった明王院は、前述の経緯から大覚寺派筆頭の中本山の寺に昇格し、末寺は四十八ヶ寺あったと伝えられている。奈良屋町の新本堂の行方であるが、草戸の常福寺と合併した際に移築され書院に使用されたと伝えている。 応仁の乱以降大覚寺は荒廃していたらしく、大覚寺再建の動きは後陽成・後水尾天皇の加護を得て、三十六世空性法親王(後陽成院の実弟)の時代から始まり、三十七世尊性入道親王(後陽成院の第五皇子)の門主時代にほぼ成し遂げられた。 一見勝成と空性法親王や尊性入道親王の接点は無さそうに見える。しかし、勝成を備南十万石の大名に引立てた恩人は徳川秀忠で、秀忠の娘和子(東福門院)は後水尾天皇の皇后となり入内している。尊性入道親王は後水尾天皇の実弟であった事から、大覚寺の再建に福山領内の真言宗寺院の増加を図った支援策は、東福門院と徳川幕府への間接的な恩返しとなり、勝成の感謝の念が真言宗寺院を纏めて大覚寺派とした。 寛永十五年八月、空性法親王は四国遍路に旅立っている。伊予の龍光院・地蔵院・石手寺の順に末寺に加え、帰途は安藝の厳島の大願寺にまで足を伸ばし、更に鞆の福禅寺と笠岡の遍照寺も末寺とするなど成果を挙げた四国遍路であった。 三、大覚寺と明王院の寺歴 改めて本末契約を交わした寛永十五年の僧を比較してみると、大覚寺は三十七世尊性入道親王の時代で、明王院の方は十七世宥将の時代であった。世代数は宥将より尊性入道親王の方が二十世も多く、大覚寺が三十世も多いことは明王院の方が遥か後世に創建された寺である事を意味している。大覚寺は嵯峨天皇の離宮で、空海が入滅してから四十四年経過した、貞観十八年(八七六)に開基された門跡寺院であった。 明王院の住職の世代数を手掛かりとして、開基年を逆算割出しする方法がある。江戸時代中期以降の明王院住職の十世の総年数を加算し、十世で割ると一世代「十九年半」の平均年数が出る。 仮に水野勝成が備後に入部した元和五年を基準年として、宥将以前の十六世の住僧に十九年半を掛算して出た答え(三百十二年昔)の年、即ち徳治二年(一三〇七)頃前後が大体の開基年の目安となる。 大正時代の明王院住職龍池(和田・片山)密雄(一八四三~一九三四)師は、安那郡道上村の出身で高野山と大覚寺六十世管長をも兼務されていた。当然大覚寺の前記文書を確認された筈である。しかし、肝心な末寺記録は何故か明王院からは今以て公表されていない。 四、明王院の梵鐘と寺伝問題 合併当時の明王院には梵鐘が無かった。宥仙は住持に就任すると梵鐘鋳造を急がせ、翌明暦三年(一六五七)十一月に完成させた。新鋳した梵鐘の池の間に、宥仙は鏨で「沼隈郡草戸之精舎中道山園光寺明王院門説大同二年平城皇帝之嘉運吾祖野山大師之開基也」と陰刻させ、開基を野山大師としていた。 この陰刻が本庄村の明王院を指すものか、それとも常福寺を意味するものか定かでない。合併した寺院の開基である以上、明王院と常福寺の二ヶ寺を記載するのが常道である。何故宥仙は二ヶ寺の開基を記さなかったのか大きな謎である。 鐘は本堂のご本尊に向かって撞くのが正式とされ、そのため鐘楼は本堂に向けて建てられている。宥仙により開基に新任された「天下りの野山大師」から送られてきた梵鐘の音に、本尊の十一面観音菩薩(平安時代後期作。余所からの移動仏像)は大変驚かれた事であろう。膨大な財力を投入して開基した地頭の長井頼秀は、知らぬ間に「野山大師」と不法登記され大憤慨した事であろう。 梵鐘は太平洋戦争にも供出されなかったらしく、三百五十余年前の鋳造当時の侭の形を今に伝えている。そのため梵鐘の南側に立てば、誰でも陰刻銘文を読むことが出来る。此の銘文が史書に記載されなかった理由は、僧侶や史家は梵鐘の年月日を読んでも銘文を省略したらしい。 宥仙の後住十九世宥翁は、梵鐘鋳造から三十三年後の元禄三年(一六九〇)に本堂の修復を行なうと、新寺伝を創作し「中道山明王密院者相伝曰、大同之年我弘法大師創基」と棟札に記し、先師の教えに背き知名度で勝負と「横滑り弘法大師」に登記替えを行った。史家と宥翁以降の現住・檀家や信者は、梵鐘の銘文を読まずに鐘を撞いていたのであろう。 その他の寺伝として、俳諧師の野々口立圃は『草戸記』に、 件の王塔(五重塔)は画工金岡(巨勢)か母此所に居住せしか、末代のじるし、又は後世菩提のために建立して と巨勢金岡の建立説を書いている。このように江戸時代になると、三人の三様の「鳶の油揚げ」作戦を展開し妄説作りに狂奔していた。 歴史学に於いては古資料優先の原則がある。『草戸記』と梵鐘と棟札の作成年代を比較すると明らかに棟札が一番遅い。福山では資料採用の原則は無視され、明王院では一番遅く捏造された寺伝の資料価値が高いとして無批判に妄信されてきた。 明王院は寺の権威付けには手段を選ばず、偽文書を作成した凄腕の怪僧がいた。水野勝成との早くからの関係を強調するためか、「元和七年の常福寺本堂再興棟札」二本と「寛永十四年の水野勝成下知状」まで巧妙に偽造し、高名な史家も史料鑑定を誤る程の出来映えであった。 五、奈良西大寺と常福寺の関係 明王院は水野勝貞の強行合併が影響したのか、常福寺時代の建物以外は中世史料を何も伝えていない。合併で常福寺は根無し草となり捏造寺伝が史実の如く公認されてきた。 常福寺の本山が奈良の真言律宗西大寺であったことは周知の事実である。明徳二年(一三九一)の『西大寺坊諸国末寺帳』と、文亀二年(一五〇三)五月の『西大寺諸国末寺帳』惣合三百十八ヶ寺の中に、草出常福寺の記載が確認できる。 西大寺と常福寺の本末関係が途絶えた年は不明で、確実な史料は残念ながら見当たらない。しかし、参考となる史料に寛永十年(一六三三)三月の『西大寺諸国末寺帳』がある。同帳には尾道の浄土寺は記載されていても常福寺は消えている。 前記の文亀と寛永の二史料を総合的に判断すると、室町戦国時代草戸千軒を繁栄に導いたのは、草戸の領主(地頭)であった備後守護山名一族と、その代官渡辺一族に越中守兼が活躍した時期である。両支配者が草戸を放棄した十六世紀の半ば頃、草戸は衰微し経済的な行き詰まりから離脱に至ったようである。 草戸の支配権について出典は明らかにされていないが、草戸と草戸千軒は無主の地であるとする誤説が近代に至って蔓延した。地頭は長井氏に続き山名氏が活躍していたことは明白な史実である。しかし、温和な福山市民は誰も異議を唱えない。 また地頭が新開開発に関与した事例も報告されている。南北朝時代安藝沼田庄の地頭小早川氏が、「沼田川の新開開発を推進していた」事例が確認されており、長井氏も草戸地先の草戸千軒を開発し繁栄策を計画し実行に移したことであろう。 長井氏は承久の乱の後に長和庄の地頭に補任された。幕府が蒙古来襲に備え防禦を進めた文永十年(一二七三)の頃、領家悲田院と下地中分を行っている。当時備後の御家人には長門防衛の軍役が下命されており、国難の非常事態に対応する海上拠点となる東側(草戸)が必要となり、悲田院に下地中分を申し込むと快く了承されたようである。 九州・長門防衛は期間不明の先が見えない軍役であり、長和庄内の港湾可能地の要求は単に長和長井氏の単一要望でなく、関東評定衆家・備後守護家・庶家一族を含む田総長井一族の要求であったと考えたい。 和与に相前後して地頭の支配地区は更に分割され、南側(田尻村と水呑村の南半分)を田総長井氏が、北側(水呑村の北半分に草戸村。神嶋村・佐波村)を福原長井氏が支配したが後に安藝の福原に移った。 元応三年(元亨元年・一三二一)常福寺の観音堂に名前を残す、地頭の長井沙門頼秀は何故此の年に建立を進めていたのであろうか。建立以前から西大寺と深い関係にあったと想定できる史料が残されていた。元亨二年は興正菩薩叡尊上人の三十三回忌の年にあたり、弟子たちは盛大な遠忌供養を計画していた。 本山の報恩供養計画を知った頼秀も、翌年の元亨二年に観音堂を完成させるべく建設途中の努力をしていた。元応三年の墨書銘は建設中に繁栄を祈って書かれたもので、落成式は本山と同様翌年に施行され盛大な大法要も営んだことであろう。 天平宝字八年(七六四)、創建時の西大寺の金堂には弥勒菩薩が祀られていた。後世の諸書は西大寺が弥勒浄土相を写した兜率天宮と称されたと伝えている。ところが徳治二年(一三〇七)二月、火災があり弥勒像が焼失してしまった。弟子達は叡尊の弥勒信仰を継承発展させるため、三十三回忌を機に弥勒菩薩像の造立に踏み切った。新造の仏像は木造漆箔の像高三百八十六cmの弥勒菩薩坐像であった。 西大寺の弥勒菩薩造立は常福寺にも当然伝えられ、頼秀は次に建立する五重塔の本尊を弥勒菩薩と定め像造し勧請した。五重塔の本尊は小型木造の像高五十二・五cmの弥勒菩薩坐像(南北朝時代作)であった。 頼秀は像造だけでなく五重塔の伏鉢にも 右夫れ普く、兜率上詣の願望を遂げ、龍花下生の来縁を結ばせじめんが為 と、陰刻銘文を彫らせ深く弥勒を崇敬していた。西大寺では 叡尊は慈尊(弥勒)説法の制に詣でてその法を聴くところに逝かれた 『叡尊上人遷化之記』 と叡尊は弥勒に深く傾倒していた。五重塔の建立は叡尊への敬慕と関連しており、叡尊への憧憬が弥勒菩薩信仰にまで昇華されていた。 江戸時代に入ると弥勒菩薩は寺僧に依り歪曲され、胎蔵界の大日如来であると伝えられてきた。五重塔の本尊弥勒菩薩は建立時より現在まで不変であるが、仏名は弥勒菩薩から大日如来に変更された。 現在五重塔の正面に立つと、寺の由来と本尊を説明した平成十一年の案内説明板がある。説明板には「本尊 木造大日如来坐像」と書かれている。別の立看板にも右から「不動明王・大日如来・愛染明王」と三尊仏が標記されている。 近年の調査でも誤伝を見抜けず、「弥勒菩薩を大日如来」とする本尊間違いの本が発刊された。国宝に指定されている本尊の誤鑑定は、日本国中に二つとは無く福山だけであろう。何れにしても県市の大失態であると同時に福山市民の恥でもある。 六、明王院の大岩盤 現在明王院の東方の前庭に立ち、堂塔を眺めると落着いた作まいの寺院建築風景を見ることが出来る。ところが八百年昔の鎌倉時代末頃となると、未開発の衝撃的な景観が残されていたことが判明した。そこには御影石の凹凸に隆起した大岩盤が連なり原生林を形成していた。 現在は土中に隠れて見えないが、五重塔と観音堂の下の大部分は岩盤を平滑に削除した上に建立されていた。その痕跡は五重塔の背後の尾根に残されており、高さ約六mもある岩盤は深く傾斜に切下げられ、盛土の上に堂塔が建設されている。 岩盤の範囲は不詳であるが、仮に五重塔の南縁側から観音堂の向拝の石段辺りまであったと仮定すると、南北の距離は二十六mとなる。また、西の尾根の下から東方に伸びた岩盤先は明らかでないが、岩盤に掘られた柱穴の位置を配慮すると約二十m程度あったと想定できる。 寺院の創建は堂塔の建立が最初と考えられるが、常福寺の場合は大岩盤の平滑化から始まった。日本には岩盤を開鑿する技術は平安初期にはなく、石加工技術が備後地方に伝えられたのは鎌倉時代末で、そこには教線の拡大を図り社会事業にも尽力した、叡尊の高弟と石工集団が岩盤開盤に従事し活躍していた。 沙門頼秀は観音堂の建立に先立ち、尾根筋と隆起している大岩盤約五百平方メートルを平滑化する大工事が可能か、前以て見極め岩盤開削工事の見通しと併行して建立に着手したのであろう。 七、西大寺と善養寺に常福寺 徳治二年(一三〇七)七月末から十数日、備中成羽川上流の航路を通すため、「笠神龍頭上下の瀬十余ヶ所」を開整する大工事が行われた。大事業を推進したのは、西大寺の末寺成羽善養寺の沙門尊海が大勧進となり、西大寺叡尊の高弟実尊が奉行となって行なわれた。石切工事は宋人石工伊行末の流れを汲む伊行経であった。此の石切技術を伝聞した頼秀は、常福寺の岩盤開鑿を実尊に要請したことであろう。 西大寺に成羽善養寺と常福寺が兄弟寺院の如く、大変深い関係あったことを記した古記録がある。永享八年(一四六三)の『西大寺坊 寄宿末寺帳』に依ると、当時西大寺内には宿坊十三ヶ坊があり、宿坊「東室一分」の十一番に善養寺、十二番に常福寺が記載されていた。 前記の寄宿末寺帳により常福寺は尾道の浄土寺(宿坊「二聖院分」)より、西大寺実尊や善養寺の方がより緊密な関係にあった事が判明した。大胆な推定を行うと実尊の後身が「東室一分」の宿坊となり西大寺内に残されていたのである。 裏付け史料は残されていないが、沙門頼秀は実尊に寺院開基と港湾開発に岩盤開鑿の技術援助を依頼し、援助の確約を得て観音堂の建立に着手したのであろう。実尊も草戸の優れた経済の拠点性に着日し、石工伊行経等を派遣して困難な開鑿工事に当らせたことはほぼ確実である。 西大寺は成羽川の工事に続き常福寺の大工事を行ったことから、宿坊帳面に善養寺の次に常福寺を記載したのであろう。寺伝として大同二年説を強調しても、岩盤平滑工事を鎌倉時代末以前に遡らすことは無理で主張は矛盾する。常福寺と成羽の工事内容を比較すると、常福寺の工事は成羽の工事と優るとも劣らない程の難事業であったと想定できる。 膨大な建設費用を要した常福寺の創建には、最初の頃は頼秀が一族の代表として建立を進めていたらしいが、幕府転覆とか武家社会の情勢が大きく変化した後は、頼秀が独力で五重塔や阿弥陀堂の建立に踏み切った可能性がある。 常福寺は強固な岩盤の上に建立されていたから、地震にも耐え七百年近くの長寿命を保つことが出来たのである。改めて頼秀の先見性に感心すると同時に、捏造史を生んだ近世史の背景の徹底的検討と、近世資料採用基準の見直しを課題としたい。 観音堂の基礎の下にある岩盤に柱穴跡があったことから、柱穴跡は再建された建物の痕跡であるとの説が主張されてきた。しかし、柱穴は足場用の柱穴として建立中の事故防止と安全対策のため掘られたものであった。足場用の証拠として、観音堂の縁側石の外側に東西各々二箇の柱穴が掘られており、距離は約十六mあるが中間に柱穴はない。 観音堂の前身小庵跡と想定された柱穴跡の図面を見ると、東西八・八mある梁には中間の支え柱穴跡が一箇もなく、西北角に必要な隅柱穴跡もなく建物の内の総柱も見当たらない。図面の通りに柱を立てると使用出来ない奇妙な建物となる。 柱穴跡を根拠として再建説の論文を書かれた人は、『国宝明王院本堂修理工事報告書』の「七十九頁の第百七図の三」の図面を模写されると、建造物の柱穴跡でないことに気付かれる筈である。再建説を書く前に原史料の分析検討を十分に行えば、誤説の「観音堂再建」説が一人歩きをする事態は避けられたであろう。 足場用の柱穴跡は観音堂下にだけ掘られていたのではなく、五重塔の周辺にも掘られていた。塔の西後方の傾斜した岩盤上には、幅九・六mの間に直径十三m以上の円形の柱穴跡が九ヶ所もある。九箇の柱穴が四方に掘られていたと仮定すると、足場用の柱穴は三十六箇必要となる。 八、国宝を建立した沙門頼秀 五重塔の建立者が明らかにされたのは、昭和十一年に郷土史家の浜本鶴賓が、(『備後史談』第十二巻十一号・明王院と草戸中洲の変遷に、五重塔の露盤銘文の研究)に沙門頼秀の名前を掲載したのが嚆矢である。爾来七十三年の長年月が経過するが研究は一歩も前進していない。 「百年河清を待つ」とは、黄河の濁流が澄むことを望んだ言葉とか。国宝の銘文が公開されて、早くも百年の四分の三もの歳月だけが無為に近付いて来る。現在の進め方では百年先でも心許なく心配である。 近世初頭まで常福寺の上空は綺麗に澄んでいた。強行合併に依る新明王院が誕生した時から、寺の上空を妖雲が漂い始め爾来三百五十余年一向に立ち去る気配は無い。妖雲を吹き飛ばすには大台風の襲来を祈願する以外に手段は無いのであろうか。 福山市で国宝の堂塔を建立した人物は、現在長井沙門頼秀が只一人である。頼秀は福山一番の文化功労者であるが、謂れの無い陰険な策謀により封印・冷遇されてきた。 地頭長井頼秀を歴史上の人物として登場させると、従来史家が「草戸は悲田院が支配していた」と、主張してきた学説が根幹から崩壊する事態となる。現在迄の学説を擁護し破綻を避けるため頼秀の業績に覆いをかけ、存在しない観音堂の再建説を強調してきた節がある。 郷土史は史家の面目を保つために存在するのではなく、郷土の発展に貢献した人物の顕彰を行うことも重要な仕事であろう。頼秀の偏見が一日も早く晴れ、明王院に頼秀の大銅像が建立される日を期待したい。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会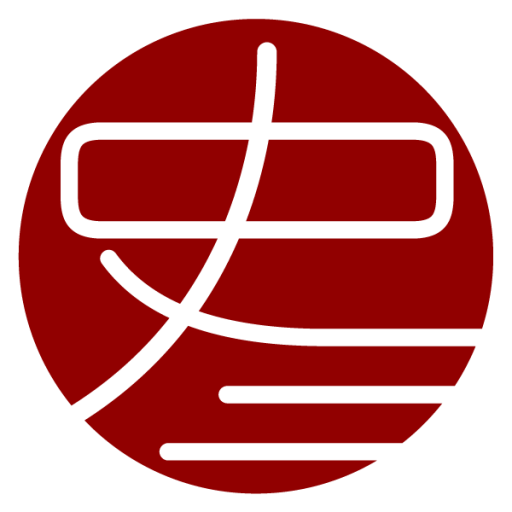
備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 中世を読む




